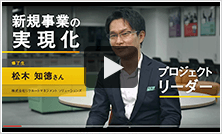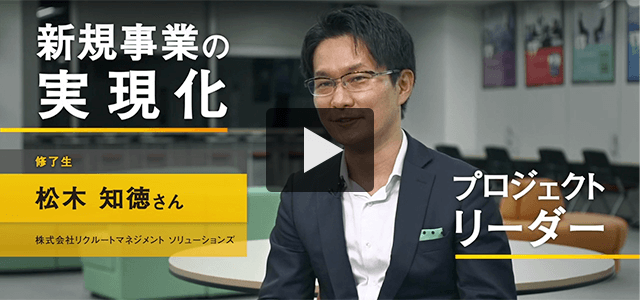杉光 一成

現職
- 知的財産科学研究所 所長
- PwCコンサルティング合同会社 顧問
出身大学
- 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 東京大学大学院(法学)修士課程修了
- 法政大学大学院(工学)修士課程修了
- 東北大学大学院(工学)博士後期課程修了
- 東京慈恵会医科大学大学院(医学)博士課程修了
プロフィール
電機メーカーの知的財産部等を経て、本学教授に着任(現在に至る)。主な著書に「知的財産法を理解するための法学入門」(旧「「理系のための法学入門」)、「意匠法講義」、翻訳書に「コトラーのイノベーションブランド戦略」、「コトラーのB2Bブランド・マネジメント」等。専門は知的財産に関する先端及び学際領域(最近ではマーケティング論と知財等)。
公職歴として参議院・経済産業委員会調査室・客員研究員、総務省「メタバース著作権委員会」委員、知的財産戦略本部・知財人財育成検討プランWG委員、工業所有権審議会試験委員(弁理士試験委員)、内閣府・知的財産戦略本部・委員等の他、多数を歴任。
日本工業所有権法学会正会員、著作権法学会正会員、情報処理学会正会員、日本知財学会正会員、日本マーケティング学会正会員。テレビ等の出演としてテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」、内閣府広報番組「ニッポンNavi」、NHK「クローズアップ現代」がある。
社会的貢献として、現在、国家試験『知的財産管理技能検定』実施機関・知的財産研究教育財団・専務理事、日本知財学会・理事、日本マーケティング学会・理事、東京大学未来ビジョン研究センター・客員研究員(シニア・リサーチャー)を務める。
これまでの主な貢献は、経産省委託事業(2005、2006)「知財人材のスキルの明確化に関する調査研究」リーダーとして「知財人材スキル標準」を開発、参議院・経済産業委員会調査室・客員研究員(2006~07)、経産省「標準化に関わる資格検定試験制度運営委員会」委員(2007~08)、(独)工業所有権情報・研修館「調査業務実施者育成研修評価委員会」委員(2007~10)、総務省「メタバース著作権委員会」委員(2009~10)、知的財産戦略本部・知財人財育成プラン検討WG委員(2011~12)、文科省委託事業・URAスキル標準策定委員会・委員(2011~14)、特許庁委託事業「公的試験研究機関知財活用支援外部委員会」委員、同「マニュアル委員会」委員長(2014~16)、(独)工業所有権情報研修館「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業選定・評価委員会」委員長(2014~現任)、特許庁「地方創生のための事業プロデューサー派遣事業」有識者委員会・委員長(2016~18)、特許庁「企業の知財戦略の変化や産業構造変革等に適応した知財人材スキル標準のあり方に関する調査研究」委員長(2016~17)、経産省委託事業・戦略的国際標準化加速事業・評価委員(2016~現任)、特許庁「弁理士に求められるスキル標準に関する調査研究 」委員長(2019)。内閣府・知的財産戦略本部「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」委員(2021~現任)。特許庁「知財情報等分析・活用を通じて実施するIP ランドスケープの具体的手法に関する調査研究委員会」委員長(2023)。
受賞歴として2008年6月に(財)機械産業記念事業財団の第1回知的財産学術奨励賞において会長大賞を受賞。「知的財産検定」(現:知的財産管理技能検定)という試験の必要性を提唱・世界で初めて開発したことにより2009年4月には経済産業省から「知財功労賞」(特許庁長官表彰)をそれぞれ受賞。
メッセージ
石油産出国は、石油資源を外国に輸出することで国富を増大させています。わが国の強みである技術力やコンテンツなどの「知的財産」も一種の「資源」ととらえることができます。外国において知的財産権を確立し、排他的に事業を展開し、あるいは現地企業にライセンスすれば、いずれの場合でも外貨を得て国富を増大させることができます。石油は枯渇すると考えられていますが、知的資源は理論的に無限に産出できるため、物理的資源に乏しいとされる我が国にとっては理想的な「資源」といえます。
他方、知的資源は「情報」ですので、その管理は容易ではなく、それを可能にするのが法制度となります。
本大学院では、我が国の知的財産に関する法制度を基礎に、諸外国の法制度や企業におけるマネジメント等を一括して1年間で集中して学ぶことができる画期的大学院です。
少子高齢化で内需の拡大も厳しい日本が目指すべきは「知的資源立国」以外にはないと考えます。本学への入学は、そのような我が国で重要な一翼を担う人材となるための第一歩となるでしょう。