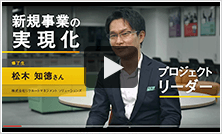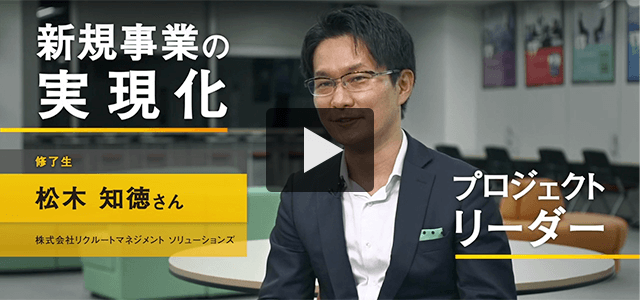- 虎ノ門大学院ブログ
- 2025年09月22日
【授業レポート】リーダーシップ特論(荒木博行)
リーダーは「失敗」とどう向き合うかが鍵?事例と実践で学ぶ
変化のスピードが速まる現代、事業が計画通りに進まないことは日常茶飯事です。このような環境で重要になるのが、リーダーが「失敗」とどう向き合うかというテーマ。
KIT虎ノ門大学院が毎年2学期に開講している「リーダーシップ特論」では、過去の失敗事例の考察を通じて、自らが取るべき未来のリーダーシップ行動をデザインします。本レポートを通して、その実践的な学びの様子をご紹介します。
| ■ 知識を行動へ。理論と実践を往復するユニークな講義 |
担当するのは、『世界「倒産」図鑑』や『世界「失敗」製品図鑑』など、数多くのビジネス書の著者として知られる荒木博行 客員教授です。90分×2コマ連続の授業が隔週で開講され、書籍で取り上げられている数々の事例を学びの題材とします。
この授業の最大の特徴は、インプットとアウトプットのサイクルにあります。講義で得た学びやフレームワークを、受講生はそれぞれの職場に持ち帰り、小さくとも実践してみる。そして次回の授業の冒頭で、その実践報告と振り返りを全員で共有することから始まります。
| ■ 現場の課題が交差する、実践報告の場 |
今回取材した5コマ目の授業も、受講生によるこの2週間の実践報告から始まりました。
「評価制度の変更意図が伝わらず部下に退職を切り出され、膝を突き合わせて対話した」「部下と許容できる失敗の範囲について対話した」など、現場のリアルな課題と、それに対する真摯なアクションが共有されます。
これらの実践報告に対して荒木先生が質問やコメントを重ねることで、議論が深まり、一人ひとりの経験が他の参加者の学びへと繋がっていきます。
| ■ ケーススタディ:「当たり前」を疑い、「考える組織」を問う |
後半は、百貨店業界のパイオニアというべき存在だった「そごう」の経営破綻をケーススタディに、荒木先生から受講生の方々へ、こんな問いが投げかけられました。
「メンバーの多くが既存のビジネスモデルを当たり前と捉え、忠実な実行者としての思考・言動が増えてきたように感じる。組織全体における考える力を育てていくためにどうすべきか?」

オンライン参加も可能、ハイフレックス形式で授業が進んでいく
この問いに対し、各グループからは「外部の視点を取り入れる」「新メンバーの違和感を尊重する」など、多様なアイデアが飛び交いました。
最後に荒木先生は、各グループから出た意見を整理。「考える組織」には、多様な意見や挑戦といった「遠心力」と、それらを束ねる「求心力」のマネジメントが必要だと解説しました。そして、求心力の核となるのが、組織の存在意義である「パーパス」です。
「我々は何のために存在するのか」というパーパスは決して揺るがず、全員で共有する。その上で、パーパスを実現するための手段(How)については、多様な議論や挑戦、つまり遠心力を最大限に奨励する。この「譲れない目的」と「自由に考えるべき手段」の切り分けこそが、変化に対応できる組織づくりの要諦であると締めくくられました。
リーダーシップや経営理論を抽象的に学ぶのではなく、受講生一人ひとりの実務経験と結びつけ、対話を通じて明日から現場で実践できる思考の型へと昇華させていくことができる。今回の取材では、そんな瞬間を何度も目の当たりにすることができました。