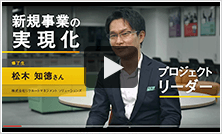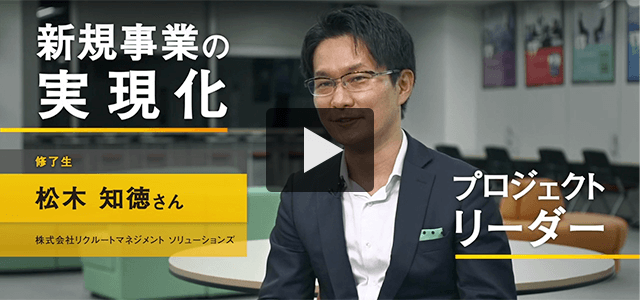産学連携・技術移転特論
University-Industry Collaboration and Technology Transfer
担当教員
受講対象者
企業等において、社外連携、研究開発、知的財産の管理活用に携わる方。大学知財部、TLO等、研究機関において知的財産マネジメント、研究企画、戦略策定を担当するコーディネーター、リサーチアドミニストレーター等、関連業務に関わる方。また将来的にこれらの業務を目指す方。これまで大学などとの協働業務を直接担当したことがない方、知財の知識がまだ浅い受講生も歓迎する
授業の主題と概要
オープンイノベーションを実際の企業活動に実装するためには、社外の新たなステークホルダーとの連携を、いかに既存の社内活動と融和させるかがキーとなります。特に、大量の情報が流通し技術の細分化が進む現在においては、企業とは全く異なる大学等の異質な組織・セクターとの協働が必須だとされています。しかし実際には、セクターの違いを乗り越え真に価値ある協働の成果を得るのは容易なことではありません。 本講議では、大学と企業という全く異なるセクターがWin-Winの関係構築を実装するための、理論的な整理、主要な連携スタイル、応用的な実践事例を、世界的なトレンドをふまえ解説します。実務に役立つ共同研究契約交渉の実際、現場で求められる知財マネジメントに加え、産学連携・技術移転業界の概観、関連する政策の概要を理解することを目指します。第2、3、5回目にはトップクラスの現役実務者より、日米の相違も含め事例含めて現状を紹介していただきます。これに担当教員の解説を加えることで、受講生の広範な興味に柔軟に対応します。なお、技術商業化特論と合わせて受講することで、日本における産学連携の全体像を包括的に理解できます。
【産学連携・技術移転特論】 ≫授業レポートはこちら到達(習得)目標
以下の項目について、実際の業務イメージ、基本となる考え方を理解することを目標とする
1)知財を中心とした企業と大学の研究開発マネジメント2)大学発の技術(知財)のライセンシングとマーケティング
講義スケジュール
| 講義 回数 |
講義テーマ |
|---|---|
| 1,2 | ・本科目の全体構成:21世紀における科学技術イノベーションの必要性、日米欧3極の科学技術政策のトレンドを概観する。また簡単な質問形式で受講生のニーズを把握し2回目以降の講座に反映する ・日本の企業と大学の協働の実際:大学技術移転業界で20年近い経験を有し、ライセンシング・マーケティング・コーディネートや各種契約交渉など産学連携に関するすべての実務に精通する平田氏より、企業との連携コーディネート、成功例や醍醐味、苦労などを直接伺う |
| 3,4 | ・日本の大学TLOの実際:最もアクティブに活動し代表的成功例といわれる株)東大TLOの創設者山本社長に、プレマーケヒング、ライセンシングなどTLO活動の実際、成功事例をその醍醐味や苦労も含めて直接伺う ・企業と大学の共同研究:第2、3回の外部専門家による講義のフォローアップに加え、技術分野・産業特性による連携スタイルの相違、共同研究に置ける基本的な論点をカバーする。大学と企業というセクターの立ち位置とその相違、研究開発への知財専門家の貢献の基本的なポイントを、実際に活用されている契約書も参考に理解する |
| 5,6 | ・アメリカの大学ライセンス有力大学であるニューメキシコ州立大学で、技術移転、大学の知財管理・活用の豊富な経験をもつ星氏より、日本との対比を含めた経験事例を伺い、アメリカトップレベルの公立大学の知財管理・活用のリアルを理解する。さらに、大学研究者の日米の違いについても視野を広げる ・大学の知的財産マネジメント:大学における知財マネジメントの概況把握、政策的、歴史的背景を紹介する。オープンイノベーションの時代に、知財の観点からもその重要性が増す、知財創出の源としての大学の位置付けを理解する |
| 7,8 | ・ケースに基づくグループディスカッションと解説(1)。外部講師による講演と合わせて、現在の日本における企業と大学の連携の実際を理解し、自組織にとって最適な連携像を概観する ・ケースに基づくグループディスカッションと解説(2)。上記に加え、産学連携専門人材に重要となる マネジメントスキルや専門知識、資質を把握する。また、代表的な利益相反事例にも触れ、リスクマネジメントについても考え方を理解する |
開講について
開講時期: 2学期
開講形態: 2コマ(180分)×4日間
講義回数: 全8回
※状況に応じて、一部変更が生じる場合もございます。予めご了承ください。
テキスト/参考図書
【テキスト】
テキストに該当する資料は、毎回授業時に配布する
【参考図書】
授業中に紹介する。講義全体に関係する参考書としては、
産学連携概況把握には「産学連携」 原山優子編著、東洋経済新聞社 (2003)
企業活動、知財の観点からは「イノベーターの知財マネジメント」渡部俊也著 白桃書房(2012)など