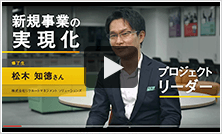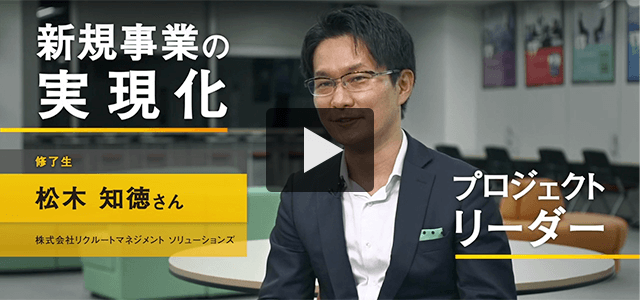技術経営要論
Essentials of Technology Management
担当教員
受講対象者
自社と自身に求められる技術経営の考え方を習得したい第一線の方。イノベーションにかかわる判断力を磨きたい管理職の方
授業の主題と概要
近年の生成AIの爆発的普及は、技術経営の考え方にも大きな影響を与えています。たとえば、チャットGPTは、これまでのAIシステムと比べて特段に技術水準が高いわけではありませんが、人間からフィードバックによる強化学習を徹底することで、きわめて短期間でユーザーフレンドリーにして成功しました。一方で、その基盤技術であるLLM(大規模言語モデル)のコスト、信頼性、などの面での根本的問題も指摘され、すでに、対立する概念の領域特化AIのSLM(小規模言語モデル)のビジネスチャンスも期待されています。これまでの技術経営は、技術を中核にしていかに企業の価値を持続的に向上させるか、を目的にして議論が進められてきました。しかし、これからの技術経営は、生成AIの例のように、人と情報を中核にして、企業価値を加速的に向上させることに目的を置くようなケースも増えて、技術経営の根本の考え方自体が多様化してきています。事実、技術マネジメントの基礎となるR&Dマネジメントやイノベーション・マネジメントに加え、カスタマーエクスペリエンス(CX)革新、シナリオ・プランニング、サービタイゼーション、エコ・システム、アジャイル・イノベーション、スタートアップとの協働、といった新たな技術経営の課題への取り組みが、多くの企業で焦眉の急となっています。本講義では、以上のような技術経営にかかわる新旧の重要テーマについて学習し、議論します。
【技術経営要論】 ≫授業レポートはこちら
到達(習得)目標
技術経営の従来の主要テーマを理解した上で、今後の市場・顧客と技術の動向を踏まえ、新たに求められる技術経営の重要課題と取組みについて考察することで、イノベーションを具体的に実現、加速させるスキルを習得することを目標とする
講義スケジュール
| 講義 回数 |
講義テーマ |
|---|---|
| 1,2 | 「イントロダクション」 従来の技術経営の背景や方法論に加え、AIやスタートアップとの協働などを含む新しい技術経営の考え方の概要を学ぶ。新旧の技術経営全体のフレームワークを理解し、技術経営に関わる主要な論点を議論する 「技術経営の実際と今後の潮流」 技術経営で実際に企業価値の向上に成功している複数の国内企業の事例を俯瞰して、それらの企業のR&Dマネジメントやデジタル戦略の特徴を理解する。また、AIにおける大規模言語モデルと小規模言語モデルの併用化、など、注目すべき複数の革新的技術の新潮流を学ぶ。その上で、技術経営で企業が、今後、考えるべき戦略的な方向性の議論する |
| 3,4 | 「イノベーション・マネジメントの考え方と方法論」 技術経営の基盤となる管理型、計画型、戦略型の3つのイノベーション・マネジメントに加え、顧客体験価値(カスタマー・エクスペリエンス)向上の視点などを市場経済や技術的な背景を含め、国内外の企業事例で学習する。さらに近未来的に有望なイノベーションの分野やテーマについて議論する 「技術経営における企業競争力の源泉」 技術経営の観点から企業競争力の源となるコア技術戦略、知財戦略、データ収集力、サービタイゼーション、などについて、具体的な企業事例をもとに学習する。その上で、シナリオ・プランニング手法など、高い不確実性への対応が重要なこれからの時代の技術経営の考え方を議論する |
| 5,6 | 「イノベーション実装のための効果的方法論」 円滑な製品開発や技術開発を阻害する原因と、それらを解消するための具体的な方策を事例で学ぶ。具体的にはパートナーシップやCVC、アウトソーシング、イノベーションチーム、イノベーションラボ、産学連携、などの事例学習をもとに、各々のアプローチの有用性や留意点について議論する 「コスト競争力の抜本的向上とエコシステム」 これまでの技術経営におけるコスト競争力向上のための方法論を事例とともに俯瞰した上で、デジタル・ツインやデジタル・ファクトリーに代表される新しいアプローチの考え方と留意点について解説する。その上で、技術経営におけるエコシステム構築の意義や重要性について議論する |
| 7,8 | 「アジャイル型イノベーションの考え方と課題」 イノベーションにおける品質管理の考え方を大きく変えるアジャイル型イノベーションの考え方を、これまでの品質管理のアプローチと対比して事例で学習する。その上で、アジャイル型開発の本質や効用・限界について議論する 「イノベーションの組織能力競争」 イノベーションの加速のために必要となる組織体制やプロセス・制度、人材管理、AI活用などを事例で俯瞰し、示唆や留意点を学ぶ。また、国内でのAIやDXのプロジェクトの成功率が低い現実を踏まえ、国内企業での成功事例をもとに、技術経営に関わる組織能力向上の要点を議論する |
開講について
開講時期: 1学期
開講形態: 2コマ(180分)×4日間
講義回数: 全8回
※状況に応じて、一部変更が生じる場合もございます。予めご了承ください。
テキスト/参考図書
【テキスト】
毎回の講義の際に配布
【参考図書】
① 三澤一文「技術マネジメント入門」日本経済新聞出版社
② ジェフ・サザーランド「スクラム」早川書房
③ 坂村健「DXとは何か」角川新書
④ 延岡健太郎「MOT(技術経営)入門」 日本経済新聞出版社
※上記は一部追加・変更となる場合もございます。また、指定テキスト及びケースなどは、
別途ご購入頂くもので、授業料には含まれておりません。予めご了承ください。