ホーム > 活動報告 > 地域志向教育研究プロジェクト(平成28年度) > 自治体と連携したプロジェクトデザイン教育活動報告
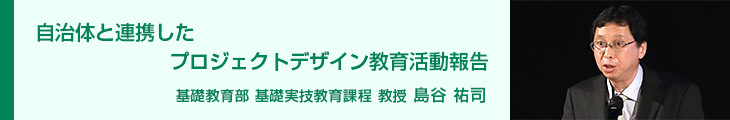
基礎実技教育課程の島谷です。それでは自治体と連携したプロジェクトデザイン教育について活動報告させていただきます。本学は、2003年に野々市市役所と、2014年に金沢市役所と連携しており、この2自治体と連携したプロジェクトデザイン教育を行っています。それが2年生の前期に必須科目として、チームを組んで身近な実社会の問題の解決活動を行う「プロジェクトデザインⅡ」です。

その内容は、高校を卒業して1年経った学生が組織のなかで他者のための活動を体験し、教員との疑似OJTを体験するものです。学生が身近な社会問題に意識を持つ動機づけとなるよう地域連携をテーマに取り上げ、興味をもった学生が取り組んでいます。
こちらがプロジェクトデザインⅡにおけるチーム活動の流れになります。
学生は地域連携テーマに対して、課題の提示、現状把握、問題の明確化、原因分析、条件把握、目標設定、解決案考案、市役所への成果報告を行います。
市役所担当課には、問題・課題の提示についてはテーマ説明会、現状把握では現地見学会、問題の明確化では中間質疑会、目標設定では評価会、成果報告の段階では部署報告を設けていただきました。
こちらが今年度の地域連携テーマの一覧になります。
野々市市役所からいただいたテーマでは「のっティを活用して工大生に野々市市をもっと知ってもらおう」「ごみ減量化への効果的な取り組みの探索」、金沢市では「森紙店の活用策」「金沢職人大学校の活性化策」のテーマを選んだチームが多数ありました。これらのテーマに対し、2年生の約3割のチームが取り組んでおります。
この統計調査の結果から、次回はとっつきにくいと思われるテーマについては、教員が噛み砕いて説明やフォローをすべきだいう改善点が見えます。
また野々市市から「県道窪野々市線の安全・安心な道路空間の創出」というテーマをいただいておりますが、これは学校の前の道路も含まれており、身近なテーマと言えます。金沢市からは伝統に関するテーマが出ているのが特徴です。
こちらの写真は昨年の4月13日に開催された「地域連携テーマ説明会」の様子です。
担当課の職員が来校し、学生たちにテーマについて説明いただきました。
 野々市市の地域連携テーマ説明会 |
 金沢市の地域連携テーマ説明会 |
次の写真は本年度開催した現地見学会の様子です。本来、現地には学生が自分達で積極的に行くべきですが難しいケースもあり、金沢市のテーマのうち3カ所については市役所の協力を得て開催いただきました。
その3カ所が工事中の森紙店と職人に話を聞く必要があった金沢職人大学校、内部の見学が必要だった湯涌地区の空き家になります。
担当課の皆様には、急な日程にもかかわらず調整いただき申し訳なかったと思っています。
次の段階として、5月18日に開催された中間質疑会の様子です。本来は学生が市役所に出向くべきですが、学生は学部外へ出たがらない傾向にあり、毎年来校をお願いしております。この場では代表チームの発表の後、各テーマごとに市役所担当課との意見交換を行いました。
続いて6月に本学で開催した評価会です。地域連携テーマに取り組んだ全83チームが一堂に会し、合同ポスター発表を行ないました。野々市市からは5名、金沢市からは10名の担当課職員が来校し、学生とディスカッションを行いました。
会場では優秀ポスターの投票も行われ、野々市市ではごみ減量化をテーマとしたチーム、金沢市は里山の活性化に取り組んだチームが選ばれております。
8月5日には各市役所の大会場で部署報告を行いました。ブースごとに成果報告を行うことで学生たちは実社会での成果報告を疑似体験できます。
各チームが同時進行で報告を行うため、市役所担当課も学生も自分の担当以外の話を聞くことができないというデメリットはありますが、今回は協議の結果このようなスタイルをとらせていただきました。
ここで学生たちの感想をアンケート結果より紹介したいと思います。
このような意見が寄せられ、学生たちは努力不足に気づき、向上心を生み、モチベーションを高く維持できたことがわかります。

最後に、高いモチベーションを維持しながら後期の活動で成果を出したプロジェクトを2例紹介します。
最初が応用バイオ学科・応用化学学科混成チームによる生ごみの減量化に対する取組です。球体コンポストを用いた生ごみのたい肥化にトライし、自分達の専門分野を活かした活動を行いました。
もう1チームは情報フロンティア学部の学科横断活動です。金沢市役所の協力を得て金沢職人大学校のPR動画を制作し、金澤町家情報館内の常設デジタルサイネージにて放映中です。
最後になりますが、野々市市役所、金沢市役所におかれては、本事業に多大な協力を賜り誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。