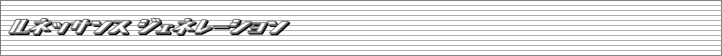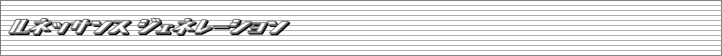<プログラム解説>
*内容は多少変更する場合があります。ご了承ください。
                                           
■イントロ [ 破局の予感 − 今、なぜカタストロフィなのか?]
出演:タナカノリユキ+下條信輔
地球規模で人類を襲った津波や地震、経済のグローバル化と環境問題、テロと文明の衝突…。私たちは今日、かつてない不安と緊張を強いられています。
予測不可能性の装いの下に突然襲うカタストロフィは、人間の叡智の限界を指し示しているように見えます。だが本当にそうなのでしょうか。数理論上の予測可能性、文明の興亡と戦争、生物種の滅亡や、個体の寿命と細胞死。文理諸学の最先端で、人の知がぎりぎりのせめぎ合いを続けています。その光芒を捉えながら、現代を生きる私たちが、今なぜカタストロフィを一人称の問題として捉え返したいのか、考えていきます。
                                           
■基本レクチャー(1) [ 文明の滅亡と環境カタストロフィ
]
出演:安田喜憲
古代文明にかぎらずマヤ文明や渤海王国など多くの文明の滅亡は、環境カタストロフィによって引き起こされてきました。そして現代文明もまた、この環境カタストロフィによって崩壊する可能性がきわめて高いと言えます。過去の文明はどのような環境カタストロフィでいつ、どのようにして、何年かかって滅亡したのか。そして現代文明はいつ、どのようにして滅亡の時をむかえるのか。いやそうではない。その滅亡を回避する道はあるのか。その道を探るのが本講演の目的です。
                                           
■基本レクチャー(2) [ 寿命、死を決める遺伝子
]
出演:相垣敏郎
私たちの身体は、年をとると次第に衰えて(老化)、ついには死に至ります。古来、時の権力者は不老長寿の薬をもとめてきたが、未だに見つかったという話は聞きません。生命の設計図はDNAであるとよくいわれますが、私たちの死もまたDNAに支配されているのでしょうか。生物の寿命は種ごとに大きく異なっています。このことは、種に固有の遺伝的性質が寿命を決めていることを示唆しています。しかし、その遺伝子はいったい何をどう決めているのでしょうか。寿命遺伝子に関する最近の研究成果をわかりやすく解説します。
                                           
■ビデオインタビュー
[ システムの “ロバストネス(頑健性)” をめぐって
]
出演:北野宏明 インタビュー=下條信輔
システムは常に一定の頑健性を持つが、撹乱要因が限界を越えるとカタストロフィが起きる。一方、システム自体が癌のように頑健で根治が難しいケースもある。ロバストネス論を切り開く北野氏に、最先端の話を伺います。
                                           
■対論 [ 心の中のカタストロフィ ]
出演:下條信輔×タナカノリユキ
「文明の興亡史から得た教訓が、現代のグローバル化によって役に立たなくなることはない。それどころか、グローバル化によって同じ危機がより破壊的になってしまうのだ」このように喝破したのはジャレッド・ダイヤモンドでした。それにしても不思議なのは、環境、経済、政治を巡る状況がグローバル化するほどに、かえって私たち個々人の心、特に潜在的な心の中身が問題となってくる構図でしょう。社会の崩壊や戦争を、なぜ人は防げないのか。危機に直面して人はどう反応するのか、そしてそれは何故なのか。死は私たちの生活をどのように拘束し、ひいてはアートやデザインの興亡にまで、どのようにつながるのか。心の中のカタストロフィ、その多様な形を考えます。
                                           
■パフォーマンス
[ カタストロフィ・スタディ Vol.
2--予測不可能性のスケッチ ]
演出:タナカノリユキ 出演:金剛地武志、JOU 他
                                           
■総括討論 [ カタストロフィの時代 ]
出演:安田喜憲×相垣敏郎×タナカノリユキ×下條信輔
古代文明の興亡は環境の人為的変化にも大きく左右されたことが、最新の研究で明らかになりました。だが人の心の問題にまで踏み込まないと、事態は解明しきれないのではないでしょうか。生と死の不条理さが、宗教をはじめとして人の精神生活の制約条件となってきました。最先端の分子生物学の知識とメタファは、そうした精神的レベルにまでインパクトを与え得るのでしょうか。
これらをひっくるめて、人は本当に予測不可能性を克服できるのでしょうか。レクチャーと対論を踏まえて、縦横に討議します。
                                           
|