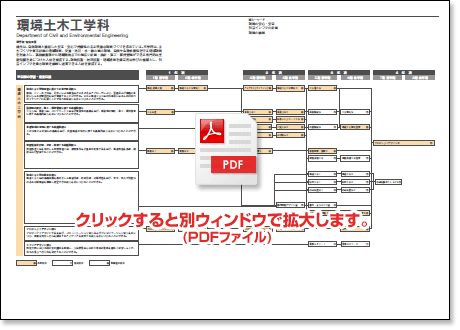環境土木工学科
学習・教育目標
現代は、自然環境と調和した安全・安心で持続性のある快適な環境づくりを求めている。本学科は、まちづくりや都市計画の地域環境、交通・河川・水・緑の国土環境、自然や生物多様性を守る地球環境を対象とし、施設構造物から地域開発までの幅広い計画・設計・施工・維持管理ができる専門的な基礎知識を身につけた人材を育成する。環境技術・防災技術・地域政策を総合的な学びの領域とし、社会インフラを含む環境を構築し運営できる人材を育成する。
キーワード
環境の安心・安全
社会インフラの計画
環境の構築
V201 環境・建築大意
Introduction to Environmental Engineering and Architecture
本学部では大学で修得した知識・技術を人間と社会に対する幅広い視野で活用し、社会に貢献できる人材の育成を目指している。そのため、この科目では学部の目標「土木・建築の各分野の領域を学ぶ」ための第1段階として、建築学・環境土木工学を構成する諸領域の概要と実際の仕事との係わりについて、教員、学生、院生、卒業生、社会人と交流、討論することにより学び、各学科で修学する意義、物事の本質を考え、自らに問いかける学習姿勢や将来目標を実現するための修学計画能力を身につけることを目標とする。
行動目標●建築・土木に関する仕事の概要とそれらの仕事の相互関係が理解できる。建築・土木を構成する領域(計画・構造・環境)の概要とお互いの関係が理解できる。建築・土木のライフサイクルを理解でき、建築・土木に関する仕事がそれとどう係わっているかを理解できる。都市計画・まちづくり、ランドスケープデザインの意義と、その建築・土木領域とのかかわりを理解できる。地域計画・インフラ計画・国土計画が社会とどう関わっているか理解できる。環境・建築学部のカリキュラムを理解し、今後の履修計画を立てることができる。
V202 土木数理
Mathematics in Civil Engineering
環境土木工学の基礎を理解するためには、多くの数学的な基礎を必要とする。解析、幾何、微分、積分などを幅広く学び、理解を深める。これらは、基礎科目や応用科目を修得するために不可欠である。
行動目標●土木数理の意義と構成、土木数理で取り扱う現象を説明できる。環境土木工学で必要とする基礎的な数学を活用することができる。
V203 測量学 I
Surveying I
人間をとりまく自然環境、人工環境を構成する「もの」の位置、大きさ、相互関連を調査・計測するための技術である測量について学習する。測量に関する法律、公共測量作業規程や測量に関する基礎的な知識を身につけるとともに、観測値処理、距離測量、水準測量、などの各種測量方法の原理、使用機器、特性など、測量の基本について学習する。新しい測量技術であるGNSSおよびGISなどの空間情報工学については紹介にとどめ、詳細は測量学 II で学ぶ。
行動目標●各種測量方法および空間情報工学の原理、使用機器の特性について説明できる。地形に応じた測量方法や目的に応じた測量方法を正しく選択できる。「空間情報工学」や「設計・計画」の見識を一層深めることができる。測量士・測量士補の国家試験のうち基礎および応用の問題を解くことができる。測量および空間情報工学の重要性について、専門基礎能力との関連を含めて説明することができる。
V204 環境土木工学設計 I
Design in Civil and Environmental Engineering I
本科目は、環境土木工学分野の導入科目である。大学で修得する環境土木工学全般の序論を体系的に学ぶことにより、環境土木工学に関する理解を深めることができ、学習目的や目標が明確になる。また、環境土木業界の分野、仕組みおよび動向を理解することで、自己の将来のキャリアパスを形成できる。
行動目標●環境土木工学の概要を理解することができる。環境土木業界の概要を理解することができる。自己のキャリアパスを具体的に考えることができる。
V205 測量学 II
Surveying II
人間をとりまく自然環境、人口環境を構成する「もの」の位置、大きさ、相互関連を調査・設計するための技術である測量の応用を身につける。測量学 II では新しい測量分野であるGIS、GNSS、リモートセンシングなどのジオインフォマチックス(空間情報工学)についての知識を得る。具体的にはトラバース測量、GNSS測量および地理情報システムなどである。講義では使用教科書の空間情報工学概論に付録のCDを活用したアクティブラーニングを取り込む(ただし測量学 I においてインストールが完了しているものとする)。
行動目標●各種測量法および空間情報工学の原理、使用機器、特性について説明できる。地形に応じた測量方法や目的に応じた測量方法を正しく選択できる。「空間情報工学」や「設計・計画」の見識を一層深めることができる。測量士、測量士補の国家試験のうち基礎的および応用の問題を解くことができる。測量および空間情報工学の重要性について、専門基礎能力との関連を含めて説明することができる。
V206 アカデミックライティング
Academic Writing
「修学基礎A・B」を引き継ぎ、土木専門分野におけるレポート作成スキルを身につける。問題発見、問題解決するプロセスにおいては、自己の考えや主張をレポートとしてまとめ、情報を発信する能力が必要である。そのために、土木の専門性に則したテーマでレポートの作成手順を学習するとともに成稿することで、専門科目のレポートおよび論文作成の基礎的能力を養う。
行動目標●土木専門分野の書式に即した適切なレポートを作成できる。テーマに即した文献や資料を探し、内容を把握し、適切に参照、引用できる。土木専門分野の書式に即した適切なレポートを作成できる。
V207 構造力学 I
Structural Mechanics I
土木構造物はその設計条件から定まる外力(荷重)に対して、安全で、かつ耐久性能を有し、経済性をも考慮して設計されなければならない。この設計に必要となる構造力学の基礎を学ぶ。まず剛体の静力学(力の合成・分解、力の釣り合い)の考え方を学ぶ。次に静定構造物に作用する外力の力の釣り合い(荷重と支点反力)の考え方を学ぶ。この学習を基に、外力によって生じる“はり”構造の部材内の内力(断面力:せん断力、曲げモーメント)の考え方を切断法により修得する。なお、はり構造の断面力の計算は、構造力学の基礎になる内容である。
行動目標●力の三要素、力の法則を理解し、力の合成・分解の計算ができる。力の効率(モーメント)を理解し、力の合成・分解の計算ができる。自由物体を理解し、力の釣り合い条件式を基に釣り合い計算ができる。静定構造の支点条件を理解し、外力の釣り合い条件から支点反力を求めることができる。静定ばりの断面力(曲げモーメント、せん断力)とその図を求めることができる。
V208 環境材料学
Environmental Materials
環境を考慮して、土木構造物の適切な設計・施工・維持管理ができるようになるために、材料科学に関する基礎的な知識を修得する。その上で、主な土木材料である、セメントコンクリート・鋼材・アスファルトなどの特長を知る。さらに、配合設計を含めて、鉄筋コンクリート工学に関する材料学的な知識を修得する。
行動目標●材料の性質を科学的に説明できる。コンクリートの特長、使用材料および主な性質を説明できる。コンクリートの配合設計を計算できる。鋼材やアスファルトの役割と特徴を説明できる。環境工学に配慮した鉄筋コンクリートの技術を説明できる。
V209 土質力学 I
Soil Mechanics I
土木構造物を設計・施工の際には、必ず土や岩が関わる。本科目では、土の基礎的な性質や現象を学び、土に関する今後の幾つかの科目の入門として、知識を身につける。具体的には、土特有の基礎状態量の定義や表現方法、締固め土の性質、土と水との関わり、地中への応力伝播を学ぶ。
行動目標●土質力学の概略を理解し、土木工学にとっての重要性を学ぶことができる。土の物理的性質とその構造が理解でき、土の状態量の定量化が学べる。盛土施工などで土を締固めた場合の力学特性の関係が説明できる。土中の水の運動、移動を理解するため、連続式と運動式を学ぶことができる。構造物の載荷に伴う地盤内応力が理解できる。
V210 水の流れ I
Hydraulic Engineering I
環境土木工学科の基礎としての水理学を学ぶ。水理学は、河川工学、海岸工学、環境工学、水道工学の基礎となっている。日本の国土面積は世界で60位であるが、EEZと含める領海の面積は世界第9位の海洋国家である。故に、海洋、海岸、河川の開発、保全に土木技術者として深く関わることが多く、深い理解が要求される。本科目では、水理学の基礎を学ぶ上で重要である流体力学の基礎、静止流体、管路の問題を理解することを目標とする。
行動目標●下記に上げる7項目に関して理解を深めることを目標とする。①流体の力学基礎、②静水力学、③流体の質量保存則、④流体のエネルギー保存則、⑤流体の運動量保存則、⑥定常管路流の水理学、⑦定常開水路流の水理学。
V211 測量実習・演習 I
Surveying Practicum / Exercises I
測量学 I では測量の総説、観測値の処理、距離測量、水準測量などの測量の基本について学んだ。これらの測量方法について実技を通して実践的に学ぶとともにレポート提出を社会における測量成果報告書と捉えて、データ整理の方法、書き方などについて修得する。測量成果の精度は構造物の設計や施工に大きく影響をおよぼすので、誤差が許容範囲に収まるよう、正しい器具の扱いかた測量方法を身につける。本科目と測量実習・演習 II および測量学 I ・ II を修得し卒業することにより国家資格である測量士補が認定される。
行動目標●各種測量機器の取り扱いができる。各測量項目の内容に応じた測量方法が理解できて、測量結果を図面およびレポートにできる。測量結果に対するプレゼンテーションができ、プロジェクト活動において迅速な問題解決ができる。「空間情報計測」および「社会基盤整備」のための具体的な計画・実施に関する見識を深めることができる。実習を通して、技術者基礎能力、専門基礎能力および技術者としての倫理感を身につけることができる。
V212 環境土木工学設計 II
Design in Civil and Environmental Engineering II
本科目では社会における問題(社会的問題)を工学的問題として発見し、それを解決するための思考行為とそれに基づく実践的なふり返り(省察)について学ぶ。社会資本整備、防災、新エネルギー創生などは社会的事業であり、その事業の遂行にあたって、環境土木技術者は重要な役割を果たす。社会的事業にかかわる問題を工学的に分析する能力は特に重要であり、本科目では実践的な技術者としての意思決定手法についてその基本を学習する。その上で、技術者としての自律的規範を身につける。
行動目標●環境土木技術者として科学的方法による技術合理性とは何か説明することができる。環境土木技術者としての必須能力を説明することができる。実践的な環境系土木技術者の省察行為を説明することができる。
V213 構造力学 II
Structural Mechanics II
構造力学 I に引き続いて、構造力学 II を学ぶ。本科目では、静定ばりの影響線の原理を学び、これを利用して支点反力、せん断力、曲げモーメントの求め方を修得する。また、材料の性質と強さとして応力とひずみの関係、各種図形の断面諸量を学んだ知識を基に、部材の応力、特にはり部材の曲げ応力とせん断力の求め方、およびそれらの図の描き方を学ぶ。
行動目標●影響線を用いて、支点反力、せん断力および曲げモーメントを求めることができる。応力とひずみの関係を説明できる。組み合わせ図形の断面諸量を求めることができる。部材の応力を理解し、はりの曲げ応力とせん断応力を求めることができる。
V214 鉄筋コンクリート工学
Reinforced Concrete Engineering
最も重要な土木材料の1つである鉄筋コンクリート部材の適切な設計・維持管理ができるようになるために、鉄筋コンクリート工学に関する構造工学的な知識を修得する。即ち、鉄筋コンクリートの3つの設計法(従来から用いられている許容応力度設計法、道路橋の設計の一部で用いられている終局強度設計法、および将来の設計法の主流になると考えられる限界状態設計法)について、基礎理論を修得する。
行動目標●鉄筋コンクリートの原理と各種設計法(許容応力度・終局強度・限界状態)の特長が説明できる。許容応力度設計法を用いて曲げ部材の設計ができる。終局強度設計法を用いて破壊強度の計算ができる。限界状態設計法による部材の終局限界状態および使用限界状態の安全性の検討ができる。
V215 土質力学 II
Soil Mechanics II
「土」の力学で特に重要な「圧密」「せん断」特性について学ぶ。「圧密」では、テルツアギの圧密理論をはじめとし、圧密沈下現象を適切に理解することを目指す。また、「せん断」では、全応力・有効応力の解析法方法や、排水条件を考慮したせん断特性と試験法の関係について学び、「土」特有の強度の評価方法を修得する。
行動目標●有効応力の概念と透水則から誘導される一次元圧密方程式が理解できる。圧密方程式中にあらわれる圧密定数やパラメータの意義を正しく理解できる。粘土の圧密特性を理解し、圧密量および圧密時間の計算ができる。土のせん断強さの概念、モール・クーロンの破壊基準を理解し、土の破壊強度を算定できる。排水条件によるせん断特性を理解し、せん断試験より得られる強度定数を正しく適用して土の破壊を予測できる。
V216 水の流れ II
Hydraulic Engineering II
水の流れ II では、水の流れ I で学んだ水理学の応用として、河川工学、海岸工学の分野において土木技術者としての基礎的な知識を身につけることを目標にする。河川工学では、河川水理特性、地形、土砂流出、治水と利水河川環境、河川構造物について一般的な知識を座学と演習問題を通じて修得する。海岸工学では、海の波の基礎、波の変形、風波、長周期波、沿岸の流れ、漂砂と海浜変形について一般的な知識を座学と演習問題を通じて修得する。
行動目標●水工、水理学は、土木工学(環境土木工学)の分野では主要力学3分野の1つであり、土木技術者としての必修の分野である。本講義では、土木技術検定試験レベルの問題解決能力の習得を目標としている。特に以下の8項目に関して理解を深めることを目標とする。①河川工学、海岸工学の概要、②河川地形、水と土砂の流出、③治水と利水、④河川環境、⑤海の波の基本特性、⑥風波の特性と波浪推算、⑦長周期波と津波、高潮、⑧漂砂と海浜地形。
V217 都市空間デザイン論
Urban and Spatial Design
現在の都市空間が抱える問題について理解しながら、都市空間デザインのあり方について考察することができる。都市の成り立ちと構造を理解し、都市空間のあり方を考察することができる。都市空間保全の考え方や方法を理解し、考察することができる。
行動目標●現在の都市空間が抱える問題について理解しながら、都市空間デザインについて考察することができる。まちづくりの考え方や方法を理解し、考察することができる。都市デザインの考え方や方法を理解し、考察することができる。
V218 土木施工学
Construction Works
環境土木技術者としての自己形成に向けて、それまでに学んできた構造力学、環境材料学、鉄筋コンクリート工学、土質力学、水の流れ、環境土木工学設計 I ・ II などを施工の視点から統合化する科目である。講義の内容は土木施工基礎となる土工、基礎工、コンクリート工である。なお、可能な限り近場の現場見学を実施し、実践的な講義運営を実施する。また、本科目は国家試験である土木施工管理技士に必須の専門を学ぶものである。
行動目標●土工の概要を理解し、土工の基本的な計画手法が説明できる。建設機械の種類と役割を理解し、その作業効率を計算によって求めることができる。基礎工の概要を理解し、その具体的な施工法を説明できる。コンクリート工の概要を理解し、説明することができる。
V219 測量実習・演習 II
Surveying Practicum / Exercises II
測量学座学では基準点測量の応用であるトラバース測量や最新のGNSS測量の基礎について学んだ。これらの測量方法について実技を通して実践的に学ぶとともにレポート提出を社会における測量成果報告書と捉えて、データ整理の方法、書き方などについて修得する。測量成果の精度は構造物の設計や施工に大きく影響をおよぼすので、誤差が許容範囲に収まるよう、正しい器具の扱いかた測量方法を身につける。本科目と測量実習・演習 I および測量学 I ・ II を修得し卒業することにより国家資格である測量士補が認定される。
行動目標●トータルステーションの取り扱いができる。GNSS測量の原理(基礎的なこと)を説明できる。各測量項目の内容に応じた測量方法が理解できて、測量結果を図面およびレポートにできる。「空間情報計測」および「社会基盤整備」のための具体的な計画・実施に関する見識を深めることができる。実習を通して、技術者基礎能力、専門基礎能力および技術者としての倫理感を身につけることができる。
V220 構造解析学
Structural Mechanics Analysis
構造力学 II に引き続いて、構造物を設計する時に必要な各種の解析法に関して、はりのたわみ、トラスの部材力の求め方を学ぶ。次いで、短柱の軸方向力と長柱の座屈荷重の求め方を学ぶ。さらに不静定構造物の解法について学ぶ。最後に連続ばりやラーメン構造を例に、たわみ角公式と節点方程式、層方程式を用いて不静定構造物を解き、Q−図、M−図の求め方を学ぶ。なお、理解を深めるため講義、例題解説および演習を連動させる。
行動目標●はりのたわみを計算することができる。トラス構造の部材力を計算することができる。短柱の応力を計算することができる。長柱の座屈荷重座屈応力を計算することができる。不静定構造物の定義を説明できる。たわみ角法を用いて不静定構造物を計算することができる。
V221 地盤解析学
Geotechnical Analysis
本科目では後学期「土質力学 II 」で学んだ知識を活用して、「土圧」と「斜面安定」について学習する。「土圧」では、まず、幾つかの土圧論について学び、擁壁などの土圧構造物に作用する土圧の考え方やその計算方法を修得する。「斜面安定」では、幾つかの斜面安定理論を学び、斜面崩壊や地すべりなどの破壊メカニズムとその斜面安定解析を修得する。なお、これらの知識は実務の分野でも重要な内容を含み、土木技術者としての不可欠な素養となる。
行動目標●ランキン、クーロン土圧の考え方が理解でき、それぞれの土圧の適用条件や計算方法が理解できる。土圧を応用した擁壁などの土圧構造物の安定計算が理解できる。斜面安定に関する基礎的な知識が整理でき、摩擦円法や簡便分割法などの考え方が理解できる。斜面崩壊や地すべりのメカニズムの基本的な斜面の設計法が理解できる。
V222 空間情報工学
Geoinformatics
地球や地域の環境管理を行うためには、地球規模や我々の身近な地域規模の自然状況や開発、土地利用状況などの各種の空間的な情報が必要となる。このような環境に関わる情報を収集し蓄積し解析するための技術である地理空間情報工学(ジオインフォマチックス)に関する基礎知識を修得する。即ち、①地理的な情報の処理を行う地理情報システム(GIS)の知識を修得する、②人工衛星画像データ処理を行うリモートセンシング技術の知識を修得する、③位置情報を活用した三次元マッピングの知識を修得する、④レーザ計測、衛星測位技術の知識を修得する。
行動目標●地理空間情報工学の概要について説明できる。地理空間情報工学に関するレポートを作成できる。地理空間情報工学に関するソフトウェアを用いてデータを処理することができる。
V223 環境工学 I
Environmental Engineering I
健康で文化的な生活と機能的な諸活動を保障するとともに、持続可能な地域を形成するためには、土地利用・都市計画・都市施設・交通・景観などのさまざまな観点から計画を立てなければならない。その策定に当たっては、長期的・広域的な視点に立って、地域の特性・課題などを正確に把握するとともに、目標実現に向けて、各種施策を総合的に検討・提示することはもちろん、社会の成熟化に伴って、さまざまな改善・改革も求められてきている。本科目では、こうした点を踏まえて、新たな地域環境計画づくりのための思想や方法について理解を深める。
行動目標●地域環境計画の意義や考え方を説明できる。地域環境計画に関する問題について自分の意見を説明し、かつその問題について異なる意見をもつ他者と議論できる。
V224 防災工学 I
Disaster Prevention Engineering I
社会の持続的発展を支える上で必要な土木構造物を守ることができるようになるため、土木構造物のメンテナンスに関する基礎知識を修得する。即ち、土木構造物を安全で快適に供用し続けることができるようになるために、鋼構造物およびコンクリート構造物の維持管理に関する知識を修得する。
行動目標●土木構造物のメンテナンスの必要性や定義を説明できる。コンクリート構造物および鋼構造物の劣化の種類とメカニズムを説明できる。コンクリート構造物および鋼構造物の維持管理方法や対策方法を説明できる。環境土木技術者としての基礎能力(自己啓発能力や技術者倫理など)を身につけることができる。
V225 地域政策学 I
Regional Political Science I
本科目は①地域政策の基本的な考え方の講義、②実際のプロジェクトとして地域政策に関わる方々の特別講義、③地域政策にかかわる計画数理などの演習を通して、地域政策の必要性とその枠組み、具体的な地域政策の展開など、キーワードに示される用語の意味を理解することを学習・教育目標とする。
行動目標●地域の概念を理解し説明することができる。地域政策の枠組みを説明することができる。地域政策の具体例を説明することができる。
V226 都市・まちづくり論
Theory of Urban Planning and Design
「都市計画・都市デザインに関する高度な専門知識を持ち、それを実務に応用することができる」という学科の教育目標の第3段階として、都市やまちを分析、考察し、理解する力を育成する。そのためには長期的な視点と明確なビジョン、そして何よりも専門的な知識が必要であり、このような専門知識として、都市のダイナミズム、環境やアメニティなどの要素、住民参加やワークショップの手法など、都市計画・まちづくりを総合的に学ぶことを目標とする。
行動目標●自分達の住むまちや都市に興味を持つことができる。都市や計画がどのような歴史的背景を持ち、何故今の社会に必要なのかを理解できる。現在の都市計画が、まだ発展過程で今後さらなる発展が必要なことが理解できる。講義によって得た知識を、都市の計画や設計に反映することができる。1級建築士や公務員試験に必要なレベルの知識を理解できる。
V227 環境土木設計演習
Design / Exercises in Civil and Environmental Engineering
環境土木技術者は、自らが持つ知識のすべてを駆使して、安全でかつ自然環境との調和を保った土木施設の計画・設計・施工を行わなければならない。これらを実践するために、環境土木設計演習では、地盤工学に関連する分野および構造物の設計に関連する分野を統合して、土木構造物の安定設計、極値外力の発生確率と統計、斜面の破壊予測など、実務上で必要となる理論・技術・工法についての知識を修得できるようになる。
行動目標●抗土圧構造物を中心とした構造物設計ができる。災害外力の基本である極値分布を学び、設計法との関連を理解することができる。斜面崩壊の中で、特に、地すべりの予知と対策を詳細に学ぶことができる。以上で修得した知識は土木技術者の実務にとって極めて重要であり、土木工学の本質が理解できる。
V228 空間情報工学演習
Exercises in Geoinformatics
環境土木設計を効果的に行う際に必要となる、コンピュータ技術を修得およびCADを用いた基本的な製図の修得を目標とする。
行動目標●CADを用いた、製図方法を修得することができる。CADを用いて図面を作成できる。
V229 土木設計学
Civil Engineering Design
鋼構造はコンクリート構造とともに土木・建築構造物の双璧をなしている。特に我が国では、耐震性や施工性などの面から、鋼構造が広く用いられている。本科目では、鋼構造物の設計理論と具体的な設計法を理解できるために、構造部材としての鋼材の特性、鋼材の接合法、各種構造部材の力学的性質、および構造物の設計規定の根拠となる原理や考え方を学習する。さらに、鋼橋梁を中心に、道路橋示方書の荷重や各種の設計規定を学習し、各部材の具体的な設計法を修得する。
行動目標●鋼構造物としての鋼橋梁の計画、種類、構造形式とその特徴を説明できる。鋼材の種類、各部材の強度と許容応力度を説明できる。溶接合および高力ボルト接合の種類、強度、設計に対する考え方や設計計算が理解できる。鋼橋梁の設計荷重の種類、設計荷重の算定および設計断面力の計算が理解できる。鋼構造物(特にプレートガーダー橋)の基本的な設計計算が理解できる。
V230 環境工学 II
Environmental Engineering II
本講義は、沿岸域の環境について学習する。海岸侵食に関する基礎的な知識を身につけ、その調査・分析、対策方法について学習する。
行動目標●沿岸域の環境問題について理解できる。基本的な波浪の現象について理解できる。沿岸域の流れが理解できる。海岸構造物への波浪の作用が理解できる。沿岸環境生態系の問題が理解できる。
V231 防災工学 II
Disaster Prevention Engineering II
防災は土木工学の主要な課題である。「災害は忘れた頃にやってくる」は寺田寅彦の有名な言葉である。もう大丈夫と思っていると突然襲って来る。阪神・淡路大震災、能登半島地震、そして東日本大震災もそうであった。過去の災害に学び、要因、誘因を分析し、適切な対策を施し、安全で効率的なインフラストラクチャーを社会に提供し、維持する責務が土木技術者には不可欠である。自然災害の領域は広く、基礎的知識を学ぶ。
行動目標●自然災害の種類や脅威を学び、それらに対する予知法や対策工法が理解できる。特に、地震時の地盤災害の予知と対策を詳細に学ぶことができる。地震、地震波の基礎知識とそれによる被害の特徴を学び、実務に備えることができる。設計震度およびそれを適用する耐震設計(主に地盤振動と基礎工)の基本が理解できる。
V232 地域政策学 II
Regional Political Science II
本科目は、①地域政策を計画・実行する上で必要となるマネジメントの基本的な考え方を講義、②実際のプロジェクトマネジメントに関わる方々の特別講義、③マネジメントに関わる考え方の演習を通して、アセットマネジメント、リスクマネジメント、プロジェクトマネジメントの意義とその概要を理解する。
行動目標●アセットマネジメントの基礎を理解し説明することができる。リスクマネジメントの基礎を理解し説明することができる。プロジェクトマネジメントの基礎を理解し説明することができる。
V233 環境土木専門実験・演習A
Civil and Environmental Engineering Major Lab / Exercises A
講義で修得した知識を実際の現象に適用するようなスキルを身につける。①種々の水の流れを把握する。②構造物の力学とその設計を理解する。③圧密を中心にした土の基礎的性質を理解する。
行動目標●実験内容を座学の知識で適格に説明できる。実験データを工学的に把握し、図化することができる。実験内容を説明できる。
V234 環境土木専門実験・演習B
Civil and Environmental Engineering Major Lab / Exercises B
これまで「土木材料学」、「鉄筋コンクリート工学」と「空間情報工学」で学んできた事項を、実験・演習を通して具体的に確認し、実践的で自主的な学習として取り組む。さらに、実験方法や実験レポートの書き方を学ぶとともに、実験内容や実験結果と考察を発表するプレゼンテーションの技法を修得する。
行動目標●コンクリートの配合設計から配合と強度の関係が理解できる。鉄筋コンクリートばりの製作と曲げ試験を通して、破壊強度と変形性能などを実験によって理解できる。地理情報システムの概要が理解できる。地理情報システムを利用して主題図を作成することができる。
V235 地域環境防災フィールド学
Field Excursion about Regional Environmental and Disaster Prevention
環境土木工学の各専門領域の広がりと相互のつながりを理解することで、より総合的に環境土木を捉える観点を養うことを目標とする。また、プロジェクトデザイン III における研究テーマや進路の検討にも各自の視点から役立てる。
行動目標●土木構造物の建設現場もしくは完成した構造物を見学し、土木分野の広がりとつながりを理解できる。環境土木技術者が修得すべき内容を理解し、自分のキャリアを具体的に描くことができる。専門科目で学習した知識を統合することができる。
V903 専門ゼミ
Preparatory Seminar for Design Project III
プロジェクトデザイン III では、自然環境と調和を図りながら、社会基盤を計画・設計・施工および維持管理でき、加えてその過程や効果についても説明できる土木技術者になるためのプロジェクト活動を実施する。専門ゼミではプロジェクトデザイン III を遂行するために必要な基礎的な知識の復習と効果的なプロジェクト活動を実現するための素養を身につける。さらに、自己の将来ビジョンを創造・設定し、技術者倫理および安全教育について修得し、将来にわたって社会の変化を分析し持続的な発展を創造できる環境系技術者としての人間力を養う。
行動目標●プロジェクトデザイン III の専門領域に関する文献を読み、各自の領域の内容の理解できる。各自の課題目的に沿った行動計画をたて、プロジェクトプロポーザルを書くことができる。具体的テーマを策定し、AV機器を利活用して効果的なプレゼンテーションができる。各研究室の行動目標に則した活動ができる。プロジェクトデザイン III を含んだ自己の将来ビジョンを創造し設定することができる。
V923 プロジェクトデザイン III
Design Project III
自然環境と調和を図りながら、社会基盤を計画・設計・施工および維持管理することができ、その過程や効果についても説明できる環境土木技術者を育成する。さらに、将来にわたって、社会の変化を分析し、環境構築と市民社会の持続的な発展を創造できる技術者としての人間力を育成する。
行動目標●自ら設定した課題の意義が説明できる。課題の解決に向けた計画が立案できる。課題の解決に向けた活動が計画的に遂行できる。活動により得られた結果を分析し整理することができる。プロジェクトの成果をレポートにまとめ、分かりやすく説明することができる。
V943 進路セミナー I
Career Planning Seminar I
自己の将来の進路、技術者としての職業観の形成を計るとともに、自分に適した進学・就職の目標を設定することおよびその目標を達成するために必要な準備・対策に自主的かつ意欲的に取り組むことを目的とする。主な課題は次の2つである。①進路アドバイザーや官庁・企業人事担当者・技術者および卒業生の講演、産業展見学や工場見学などを通して職業に対する意識向上を計り、自分に適した進路の在り方を探究する。②資格取得、一般常識、総合適性検査(SPI)など準備・対策に比較的長期を要する課題に計画を立てて着手する。
行動目標●人生設計と進路との関係を自ら深く考察できる。自分の適性な進路を発掘すべく、それに必要な思考や行動ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を、他人にも理解できるように論理的に説明できる。進路に対する目標を達成するために必要な知識、能力、素養などを調査し、自ら準備・対応ができる。
V953 進路セミナー II
Career Planning Seminar II
進学・就職の目標を明確にするとともに、その目標を実現するために、自己発掘と自己啓発による人間形成を図ることを目的とします。主な課題は次の2つです。①自己分析や企業研究を通し、職業観を明確にするとともに、自ら進学・就職の進路決定や能力・適性に応じた職種や企業の選択ができるようにする。②進学および志望する職種、企業で要求される適性、学力、素養、資格を調査・研究し、その対策・準備として、自ら一層の向上を目指す。
行動目標●人生設計と進路との関係を自ら深く考察できる。自分の適正な進路を発掘すべく、それに必要な思考や行動ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を、他人にも理解できるように論理的に説明できる。進路に対する目標を達成するために必要な知識、能力、素養などを調査し、自ら準備・対応ができる。