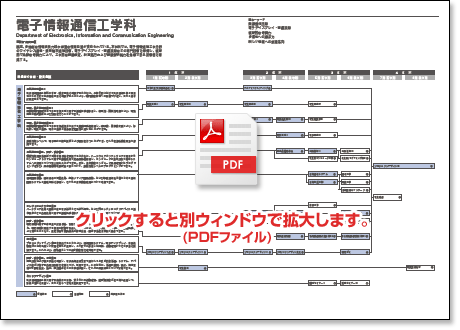電子情報通信工学科
学習・教育目標
現在、多機能な情報表示方法や高速な情報伝達が求められている。本学科では、電子情報通信工学分野のワイヤレス通信・携帯端末通信技術、電子ディスプレイ・音響技術などの専門技術を修得し、複眼的で柔軟な考察力により、工学的な課題設定、計画遂行および課題解決能力を発揮できる技術者を育成する。
キーワード
無線通信技術
電子ディスプレイ・音響技術
複眼的な考察力
多様性への適応力
新しい価値への創造志向
E401 工学大意(電子情報通信)
Introduction to Engineering(Electronic, Information and Communication Engineering)
社会を支える「ものづくり」の三大技術である機械分野、電気・電子分野、情報分野の技術について、工学と社会とのつながり、歴史および現在、未来の技術について学び、「自ら考えて行動する技術者」としての第1歩を歩み出す意識を明確にする。各分野における学ぶ領域、学問の拡がりを学び、各自の将来の目標、夢を実現するためのキャリア形成を意識して、修学計画能力を身につけ、今後の学習姿勢を確立する。「覚える・暗記する」といった学習能力に加えて物事の本質を論理的に考える力(科学力)、デザイン力の醸成を目標とする。
行動目標●現代社会における工学部の役割を理解し、自身の修学計画を立案することができる。電子情報通信工学科での学習内容を理解し、どんなことを学ぶかを説明できる。電子情報通信工学の体系(システムの全体像)について理解し、自分自身の学習目標を説明できる。電気回路の基礎について理解し、それらの概略を説明できる。電気および情報通信の応用例および情報通信工学の重要性について理解し、それらの概略を説明できる。自身のキャリア形成プロセスを自身の言葉で述べ、それを第三者に伝える事ができる。
E402 電気回路 I
Electric Circuits I
当科目は電気系科目の中で基礎となる重要な科目であり、電気回路に関する基礎知識を修得し、その物理学的・数学的考察によって、電気回路の特性解析および設計を行うことができる能力を養う。はじめに抵抗(R)のみの回路が直流電源に接続された場合について学習し、次に抵抗(R)、インダクタンス(L)、静電容量(C)およびそれらの組み合わせからなる回路が交流電源に接続された場合について学習する。さらに記号法による回路の計算方法を修得する。
行動目標●直流回路におけるオームの法則とキルヒホッフの法則を説明できる。また、これらを用いて直流回路の計算ができる。直流回路における最大電力条件を計算できる。正弦波交流の平均値や実効値の計算ができる。また、R、L、Cの回路解析ができる。複素数を用いる記号法により回路解析ができる。また、回路の各部の電圧・電流のフェーザ図を描ける。
E403 電気回路 II
Electric Circuits II
「電気回路 I 」の復習を含め、本講義では、抵抗(R)、インダクタンス(L)あるいは静電容量(C)およびそれらを組み合わせた基本回路からやや複雑な交流回路までを扱う。交流回路の計算では、フェーザと複素数を用いたいわゆる記号法を用いて解くのが常識と言っても過言ではない。ここでは、記号法による回路解析手法を修得する。本講義後、「電気回路 III 」において、さらに高度かつ複雑な電気回路の解析手法について学習する際のベースとなる。
行動目標●記号法によりR-L、R-CあるいはR-L-C直列回路や並列回路の回路方程式を立て、回路解析ができる。記号法で直・並列回路の位相条件問題や交流電力の基本的な問題が解ける。記号法を用いて直列共振回路や並列共振回路の問題が解ける。記号法を用いて電力の問題が解ける。
E404 電気製図
Drawing Skills in Electrical Engineering
電気に関連する製図について学習する。製図と規格、線の用法などの製図の基礎を学ぶとともに、基礎的な機械要素の製図、電気回路や電気機器の設計で必要となる回路図の製図を行い、製図の読み方、描き方について修得する。
行動目標●製図で用いられる線種、文字、記号が理解でき、他人に説明できる。電気回路をJIS規格にあった方法で描くことができ、他人に説明できる。簡単な機械製図が理解でき、他人に説明できる。
E405 アカデミックライティング
Academic Writing
「修学基礎A・B」を引き継ぎ、各専門分野におけるレポート作成スキルを育成する。問題発見、問題解決するプロセスにおいては、自己の考えや主張をレポートとしてまとめ、情報を発信する能力が必要である。これを「個人」の能力として身につけさせるために、学科の専門性に則したテーマでレポートの作成手順を学習するとともに成稿することにより、専門科目のレポートおよび論文作成の入門として位置づける。
行動目標●電子情報通信の分野における問題を発見し、レポートのテーマを設定できる。電子情報通信の分野における情報を収集・分析・整理することができる。電子情報通信の分野に則したレポートが作成できる。
E406 電気磁気学 I
Electromagnetics I
「電気磁気学 I 」は電気電子・情報通信分野における重要な基礎科目であり、2年次以降に履修する専門科目を理解するのに必須である。本講義では「電気磁気学」におけるさまざまな物理現象を解析するのに必要な基礎数学を修得すること、主として静電場における電荷、電界、電位、静電容量に関する基本法則を理解すること、静電界の諸問題への解答能力を修得することを「学習・教育目標」とし、続く「電気磁気学 II 」、「電気磁気学 III 」の理解に必要な基礎学力を身につける。
行動目標●電荷の性質、電荷間に作用するクーロンの法則が理解でき、静電界に関する基礎的な問題が解ける。電荷が形成する電界と電位の関係を理解し、ガウスの法則を用いて種々の電荷分布に対する電界と電位の基礎問題が解ける。導体系の静電容量、静電エネルギー、複数のコンデンサの直並列接続による合成容量に関する基礎的な問題が解ける。誘電体の電気分極を理解し、誘電体を含む導体間の静電容量および静電エネルギーに関する基礎的な問題が解ける。
E407 電気回路 III
Electric Circuits III
「電気回路 I 」および「電気回路 II 」の復習を含め、本講義では、抵抗(R)、インダクタンス(L)あるいは静電容量(C)およびそれらを組み合わせた基本回路からやや複雑な交流回路までを扱う。交流回路の計算では、フェーザと複素数を用いたいわゆる記号法を用いて解くのが常識と言っても過言ではない。ここでは、記号法による回路解析手法を修得する。本講義後、「電気回路 IV 」において、さらに高度かつ複雑な電気回路の解析手法について学習する際のベースとなる。
行動目標●記号法を用いて最大電力問題が解ける。記号法を用いてフェーザ軌跡の問題が解ける。相互誘導現象について説明でき、記号法を用いて基本的な相互誘導の解析ができる。二端子対回路で、少なくともZ、Y、Fの各マトリクス表示を用いた計算や、T形およびπ形等価回路への変換ができる。
E408 電子工学
Electronic Engineering
情報、通信から電力の分野まで幅広く利用されている半導体電子デバイス分野を主に扱う。具体的には、pn接合の基礎の理解やバイポーラ形およびMOS形トランジスタの基本構造および動作原理を学習する。さらに、それらの知識を基に集積回路の種類や構造への理解を深める。また、光電変換素子など各種電子デバイスについて、必要最低限の物理と基本構造、動作原理ならびに応用事例を学ぶ。本科目は後に開講される「物性工学」を理解する上でのベースとなる。また同時開講の「電気材料」では半導体以外の材料や各種素子について学ぶ。
行動目標●半導体のエネルギーバンド図および半導体中のキャリアの基本的な挙動と電流の関係を説明できる。半導体のキャリア濃度、フェルミ準位、導電率など基本的な物理量を定量的に求めることができる。半導体デバイスの動作原理を、エネルギーバンド図を用いて説明できる。各種の電子デバイスの基本構造、動作原理および特徴を説明できる。光電変換デバイスの基本構造、動作原理および特徴を説明できる。集積回路(IC)の種類、構造および主要な作製プロセスを説明できる。
E409 電子材料
Electronic Material Engineering
電力からエレクトロニクス分野の基盤となる電気機器・電子デバイスの研究開発や応用研究を行っていく上で必要となる導電体、超伝導体、半導体、誘電(絶縁)体、磁性体材料の基本的物性について学習する。各材料のデバイスや機器などへの適用例についても学習する。講義を通して材料の重要性を認識できるようにする。
行動目標●固体中の電子状態、原子の結合様式、バンド構造などの基礎的事項について説明できる。導電材料について、それらの特徴・用途について説明できる。半導体材料について、それらの特徴・用途について説明できる。誘電体材料について、それらの特徴・用途について説明できる。磁性体材料について、それらの特徴・用途について説明できる。
E410 電気磁気学 II
Electromagnetics II
「電気磁気学 II 」は電気・電子・情報・通信工学分野における根幹をなす基礎科目のひとつであり、その修得は他の科目を理解するために必須である。本講義では「電気磁気学 I 」(3期)で学んだ基本的な知識を基に、ベクトル解析、微分学、積分学などの数学的考察を用いて、電界、磁界およびそれらの相互作用に関する基礎的かつ重要な電磁現象に関する問題を解き、定量的に理解できることを「学習・教育目標」としている。
行動目標●電流とその周りの磁界の関係を理解し、ビオ・サバールの法則、アンペアの法則を用いて基礎的な磁界問題が解ける。磁界と電流の関係を理解し、磁界中にある電流の流れている導線に働く電磁力を計算できる。磁界が電流におよぼす作用を理解し、電磁誘導に関するファラデーの法則を用いた基本的な計算ができる。自己および相互インダクタンスについて理解し、関連した基礎的な問題が解ける。
E411 物性工学
Physical Electronics
情報通信システムのハードを支える光電子工学、光波工学、レーザ工学などの光エレクトロニクス分野においては、材料物性に関する幅広い理解が不可欠である。本講義では情報通信材料工学における技術開発の基盤となる材料物性の基礎を学習する。具体的には、量子論の基礎、結晶構造、固体の電気伝導・誘電的特性・磁気的特性、および物質と光の相互作用、半導体の光励起、光吸収、発光過程などの光学的物性と主な光電変換デバイスの構造と動作を学び、固体内の電子および光の挙動を理解する。
行動目標●古典物理学の限界と量子物理学誕生の必要性、物質波およびボーアの原子モデルを説明できる。結晶構造、結晶の結合力および格子振動を説明できる。固体中での電気伝導機構および超伝導を説明できる。固体の光学的物性の基礎を理解し、光の吸収・発光現象および主な光電変換デバイスの構成と動作原理について説明できる。電子・電気材料や電子デバイスに利用されている誘電特性を説明できる。電子・電気材料や電子デバイスに利用されている磁気的特性を説明できる。
E412 回路過渡応答論
Transient Responses in Linear Circuits
状況や条件が変化した時、ある状態が安定な状態に落ち着くまでの過渡期に生じる現象が過渡現象である。本科目は、電気回路の回路方程式(微分方程式)を立て、初期条件を入れて過渡状態にある電気回路の電圧、電流、エネルギーなどを計算する方法を学ぶ。またラプラス変換とその応用を学ぶことにより複雑な回路の過渡現象を解析する方法を学ぶ。これらにより、電気回路で生じる各種過渡現象を理解する。当該科目の内容は、後に開講される「自動制御」において学ぶ自動制御理論やそれを使った応用を理解する上でのベースとなる。
行動目標●電気回路を見て、回路方程式(微分方程式)を立て、初期条件を書くことができる。電気回路を見て、初期条件を見つけて適用することができる。微分方程式を解いて、過渡現象を表す式を求めることができる。過渡現象を表す式を基にして、それを図示することができる。ラプラス変換法を理解できる。ラプラス変換を用いて、電気回路の過渡現象を解くことができる。
E413 電子回路 I
Electronic Circuits I
電子回路はエレクトロニクスの技術者や研究者にとって、非常に重要な学問である。本講義では、最初にダイオードやトランジスタの基本動作を主体としたアナログ電子回路の基礎について学習する。次に、バイポーラトランジスタを用いた基本増幅回路を理解することにより、アナログ電子回路の考え方や設計法を身につける。さらに、FETやオペアンプの回路についてもその動作原理と回路を具体的に学習する。また、デジタル電子回路における最も基礎的な論理回路についても学ぶ。
行動目標●ダイオード、トランジスタの働きを説明できる。トランジスタ増幅回路の小信号等価回路を描ける。オぺアンプを用いた回路を設計できる。2進数や16進数の進数変換ができ、それぞれ10進数との関係についても説明できる。ブール代数の計算や論理回路の簡単化ができる。OR回路やAND回路などを説明できる。
E414 電子通信計測
Electronic Instrumentation in Information and Communication Engineering
電気計測は、計測器を使って電圧、電流、電力、周波数、回路素子の特性などの主に電気的な量を測る手立てである。この科目では、電子情報通信工学分野で必要とされる電気計測技術の基礎が理解できるように、単位や測定用語の意味と使い方、物理量の計測手法、主要な計測器の構成と測定原理などを修得する。
行動目標●計測の基礎となるSI単位や測定に関する用語を使いこなすことができる。主な電気計器(アナログ計器、電子計器、デジタル計器)の構成と測定原理が説明できる。計測対象量に合わせて適切な測定手段、測定器が選択できる。
E415 自動制御 I
Feedback Control I
産業界や家庭内でもマイクロコンピュータを用いた自動制御機器が数多く使用されている。現在の工学分野では、自動制御理論を学習し、実践することは非常に重要こととなっている。本科目では、制御系の数式化、ラプラス変換、ブロック線図、伝達関数を用いたフィードバック制御系の考え方を学び、さらに伝達関数の特性、制御系の安定性、過渡応答特性、定常特性などを学習する。また、それらを応用したフィードバック制御系の設計を行うことができることを目標とする。
行動目標●自動制御で用いられる要素の種類とそれぞれの特徴を理解できる。ラプラス変換、ラプラス逆変換を理解できる。伝達関数を理解でき、自動制御系を伝達関数とブロック線図で表すことができる。伝達関数表現によるフィードバック制御系の基本設計ができる。自動制御系の安定性の評価方法について理解できる。
E416 情報通信システム
Communication and Network Systems
高度情報化社会の進展とともに情報通信システムの重要性が高まっている。情報通信工学を専門とするにあたって、情報通信システムの基礎と社会基盤を支える情報通信ネットワークの構成を理解することが重要である。さらに、コンピュータと通信が結びついたデータ通信、遠距離通信に用いる衛星通信、大容量伝送できる光ファイバ通信、および多様化する移動通信についてシステム的観点から理解する。
行動目標●情報通信システムの基本構成とその構成要素について説明できる。各種情報通信システムの主要な通信方式について説明できる。各種情報通信システムの設計の基礎となる簡単な計算ができる。情報通信システムに用いる主要な用語を説明でき、簡単な応用ができる。
E417 情報伝送工学
Transmission of Electronic Information
情報通信工学を学ぶ上で必要となる情報信号の取り扱い方および情報信号を伝送する技術の基礎を取り上げる。最初に、アナログ信号およびデジタル信号の解析手法であるフーリェ級数・フーリェ変換について学ぶ。その中で信号の時間領域での振る舞いと周波数領域での振る舞いの関係を学ぶ。さらに振幅、周波数変調などのアナログ変調方式の原理と性質を学び、変調波の周波数スペクトラムの様子を学ぶ。最後に情報源符号化の方法を学び、アナログ信号の標本化に関する基本的な要件である標本化定理を学ぶ。
行動目標●周期関数のフーリェ級数展開を行うことができ、その意味を理解することができる。フーリェ変換・逆フーリェ変換を行うことができ、その意味を理解することができる。信号の時間域と周波数域の間の変換ができ、周波数帯域、フィルタの特性が説明できる。アナログ変調(振幅変調)の原理を説明できる。アナログ変調(周波数変調)の原理を説明できる。情報源符号化(PCM)の流れを説明でき、標本化周波数の条件(標本化定理)を理解することができる。
E418 電気系コンピュータ工学
Computer Engineering for Electrical Engineers
コンピュータは、スーパーコンピュータからパソコンやマイコンに至るまで、産業界においても、また、個人用にも広く利用されている。本科目では、コンピュータの基礎を身につけることを目標とし、特に、コンピュータの基本構成と動作原理の理解に重点を置く。具体的には、機械語命令と命令実行サイクルおよび関連するハードウェアなどについての確実な理解を目指す。なお、コンピュータは種々の制御に用いられることも多いので、他の講義と関連づけて理解するとなお良い。
行動目標●コンピュータの基本構成および仕組みを理解し、説明できる。C言語、アセンブリ言語、機械語で記述された簡単なプログラムを関連づけて理解し、説明できる。CPUの基本構成およびCPUにおける機械語命令の処理の流れを説明できる。記憶装置および入出力装置について基礎事項を説明できる。コンピュータの高性能化について基礎事項を説明できる。
E419 音響工学
Acoustic Engineering
日常生活の中では、あらゆる種類の音があふれており、音は我々の生活に不可欠なものである。本科目はその音について、工学的観点から、概要および基礎について学習する。具体的には、音響の基礎とオーディオの基礎について理解し、説明できるようになる。音波の物理特性を数学的に表現し、現象を解析できるようになる。日常生活における室内音響と聴覚に関する音の振る舞いを理解し、工学的に応用できるようになる。
行動目標●音響の基礎について理解し、説明できる。オーディオの基礎について理解し、説明できる。音波の物理量を用いて音波の物理特性を表現し、現象を解析できる。室内音響に関する音の振る舞いを理解し、工学的に応用できる。聴覚に関する音の振る舞いを理解し、工学的に応用できる。
E420 電気回路 IV
Electric Circuits IV
電気電子工学、情報通信工学の最も基礎となる科目の1つが電気回路である。この科目では、情報通信分野で特に重要となる分布定数回路について学ぶ。分布定数回路については、高周波の信号を扱う回路や装置を扱う際に必要となる伝送線路の理論を理解し、スミスチャートや散乱行列を用いた、実践的な設計の基礎知識を得ることを目標とする。
行動目標●分布定数回路と集中定数回路の違いを説明できる。基礎的な分布定数回路の回路計算ができる。スミスチャートの使い方がわかる。整合回路の計算を行うことができる。
E421 電子回路 II
Electronic Circuits II
電子回路はエレクトロニクスの技術者や研究者にとって、非常に重要な学問である。本科目ではデジタル電子回路における基礎的な論理代数や論理回路について学習し、各種論理回路の動作原理を理解することを目標とする。講義においては、AND、OR回路などによる組み合わせ論理回路のほか、フリップフロップ、カウンタなどの順序回路、A/D変換器などのデジタル機能回路について学び、それらの動作原理について説明できる力を養う。
行動目標●組み合わせ論理回路の基本設計ができる。パルス回路(微分回路や積分回路、マルチバイブレータ)が説明できる。4種類のFFの特徴と基本動作原理が説明できる。基本的な同期式/非同期式カウンタ回路の設計ができる。A/DやD/A変換回路の動作原理が説明できる。
E422 電気磁気学 III
Electromagnetics III
「電気磁気学 III 」は電気電子・情報通信工学分野を学ぶための基礎となる重要な専門科目の1つである。その修得は、これに続く他の専門応用科目を理解するために必須である。本講義では「電気磁気学 I 」「電気磁気学 II 」で学んだ基本的な知識を基に、磁性体、磁気回路、インダクタンス、電磁波の性質などについて重点的に学習する。また演習問題に多く取り組み、電気磁気学の基礎的な問題を解く力を修得する。
行動目標●磁性体中の磁化現象を理解し、磁界の計算に関する基礎的な問題が解ける。磁性体で構成した磁気回路を理解し、磁束や磁界を求める基礎的な問題が解ける。電磁波の性質を理解し、関連した基礎的な問題が解ける。
E423 光エレクトロニクス
Optoelectronics
本科目は、光エレクトロニクスの概要および基礎について学習する。具体的には、光の性質、反射・屈折現象、干渉・回折現象、発光・光吸収現象などを定性的に扱うことができる。また、レーザ、発光ダイオードなどの光源の種類、動作原理を説明できる。受光素子についても説明ができる。光ファイバの原理についても説明できる。本科目で学んだ事柄は「電子ディスプレイ工学」などの専門科目につながる。
行動目標●光の特徴を決める基本的な性質を理解できる。光の反射と屈折、干渉と回折について基本的な性質を理解できる。光の吸収と発光のメカニズム、レーザの発振原理について基礎的なことを説明できる。光源の種類、構造および発光特性について基礎的なことを説明できる。
E424 電気系プログラミング演習
Programming Practice for Electrical Engineers
電子情報通信分野において、計算機は多種多様な問題を解決するために必須の道具となっている。電気電子機器の制御や設計のためにもソフトウェアは欠かすことができない。電子情報通信分野の技術者は、プログラミングと数値解法の技法を体系的に学び、身につけておく必要がある。本科目では、C言語によるプログラミングの基本的技法を、主に演習を行うことにより、修得することを目標とする。また、電子情報通信分野における基礎的な問題を、数値解法により解けるようになることを副次的目標とする。
行動目標●C言語で書かれたプログラムを読んで理解することができる。C言語で、基礎的なプログラムを書くことができる。簡単な問題について、アルゴリズムとして記述することができる。電子情報通信分野の基礎的な問題を、計算機を用いて数値解法により解くことができる。コンピュータ工学の基礎であるデータ表現と論理回路について他人に説明できる。
E425 自動制御 II
Feedback Control II
現在の工学分野では、自動制御理論を学習し実践することが、非常に重要なこととなっている。本科目では、ラプラス変換、伝達関数、ブロック線図などの取り扱いに習熟し、古典制御理論に基づくフィードバック制御系の設計法を学習する。さらに、状態方程式を用いて線形システムを微分方程式によって表現し、制御系を解析および設計する現代制御理論の基礎を学習する。
行動目標●ラプラス変換、伝達関数、ブロック線図を使いこなすことができる。自動制御系の設計に際し、特性補償法を理解でき、基本的なフィーバック制御系の設計ができる。制御系を状態方程式で表すことができ、伝達関数との関係を理解することができる。古典制御理論・現代制御理論の両方について、安定判別法を理解できる。状態フィードバックについて論じることができる。
E426 通信工学
Communication Engineering
通信工学を学ぶ上で必要となる通信系の構成、情報・信号の取り扱い方、通信品質を悪化させる要因とC/N比、デジタル変復調、多重化、誤り制御の方法を取り上げる。各項目に対して、その考え方、原理的な振る舞いを与える理論式、計算法に重点をおいて学ぶ。
行動目標●電気通信の基本的事項と情報の取り扱い方を理解し、説明できる。ベースバンド伝送理論の原理を理解し、簡単な計算ができる。デジタル変復調の原理を理解し、簡単な計算ができる。通信を悪化させる要因の表し方を理解し、C/N比の簡単な計算ができる。多重化の原理を理解し、簡単な計算ができる。誤り制御の考え方を理解し、原理を説明できる。
E427 電波工学
Electromagnetic Wave Engineering
本科目では電磁波によるエネルギーの伝達、電磁波の放射について学び、電磁波について基礎的な計算を行う。電磁波の送信と受信に欠かせないアンテナの諸特性を理解し、設計に必要な基礎的な計算を行う。また、媒質中およびその境界での電磁波の振る舞いについて学び、大気中の電波伝搬の形態を理解する。さらに、電波を通信に用いる場合の基本となる電波の送信と受信について学び、C/N比の基礎的計算を行う。
行動目標●電波の概念と役割を理解し、応用される仕組みを説明できる。電磁波の性質と伝搬について理解し、基礎的な計算ができる。アンテナの概念を理解し説明でき、基礎的な特性の計算ができる。電磁波の振る舞いを理解し、代表的な概念について説明できる。電波伝搬の基礎を理解し、代表的な概念について説明できる。電波の送信・受信について理解し、基礎的なC/N比の計算ができる。
E428 電子ディスプレイ工学
Electronic Display Technology
コンピュータをはじめとする各種の情報機器、情報システムと人間をつなぐマンマシン・インタフェースとして重要な情報ディスプレイについて、その構造、動作原理、応用などの基礎知識と基本技術が理解できる。具体的には、ブラウン管、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ(PDP)、有機ELディスプレイ、電子ペーパーなどの情報表示システムを学習するとともに、人間工学的な観点から、情報ディスプレイの画像認識、画質評価技術の重要性が理解できる。
行動目標●ディスプレイの画質評価方法を数個の例を挙げて説明できる。代表的な発光形情報ディスプレイの構造と動作原理について説明できる。代表的な非発光型情報ディスプレイの構造と動作原理について説明できる。各種のディスプレイの応用技術について説明できる。
E429 情報通信ネットワーク
Network Technology of Information and Communication
本科目では、通信ネットワークがどのような構成で作られ、どのような使われ方をしているかを理解する。電話を中心とした現在までのネットワークのポイントを理解し、加えて、今後のIPネットワークやブロードバンドネットワークを理解する。
行動目標●ISDN、SDHについて説明できる。LANについて説明できる。インターネットについて説明できる。ブロードバンドネットワークについて説明できる。
E430 電子情報通信専門実験・演習A
Electronic, Information and Communication Engineering Major Lab / Exercises A
「プロジェクトデザイン入門」、「プロジェクトデザイン I ・ II 」、「プロジェクトデザイン実践」、専門科目などで学習した理論および手法を生かし、電気エネルギー技術、情報・制御技術、エレクトロニクス技術に関するさまざまな「実験・演習」を行うことで、技術者に必要な“問題発見・解決能力”、“分析・解析能力”、“専門的な基礎能力”、“工学的な応用能力”を修得し、次年度の「プロジェクトデザイン III 」で活用できるようにする。なお、履修者が取り組む「実験・演習」テーマは「電子情報通信専門実験・演習B」とは異なる。
行動目標●実験を正確に実施できる。実験より得られた結果を、整然とまとめることができる。起承転結のあるレポート作成ができる。
E431 電子情報通信専門実験・演習B
Electronic, Information and Communication Engineering Major Lab / Exercises B
「プロジェクトデザイン入門」、「プロジェクトデザイン I ・ II 」、「プロジェクトデザイン実践」、専門科目などで学習した理論および手法を生かし、電気エネルギー技術、情報・制御技術、エレクトロニクス技術に関するさまざまな「実験・演習」を行うことで、技術者に必要な“問題発見・解決能力”、“分析・解析能力”、“専門的な基礎能力”、“工学的な応用能力”を修得し、次年度の「プロジェクトデザイン III 」で活用できるようにする。なお、履修者が取り組む「実験・演習」テーマは「電子情報通信専門実験・演習A」とは異なる。
行動目標●実験を正確に実施できる。実験より得られた結果を、整然とまとめることができる。起承転結のあるレポート作成ができる。
E432 電気応用
Electric Power Applications
電気エネルギーを、光や熱、あるいは力学エネルギーに変換することは容易である。しかも、変換量を容易に制御できるので、家庭や産業で広く実用されている。本科目では、体系的に分類された電気エネルギー利用形態の概要を学習する。即ち、ビルや工場の各種設備、あるいは鉄道、飛行機、自動車などの交通施設で用いられる電動機と照明、電熱、電気化学、および自動制御技術について、さらにその他の電気応用の超電導、静電気、磁気応用などについて学ぶ。
行動目標●電動機の鉄道、自動車などの産業分野における応用例について概略を説明できる。各種照明用光源や照明方法について説明でき、簡単な照明計算ができる。電気加熱と熱回路の特徴や具体例などについて説明できる。電気分解と電池の電気化学反応の相違や、一次、二次電池の種類や特徴について説明できる。フィードバック制御における伝達関数や安定性判別の概要と特徴について説明できる。これら以外の電気応用としての超電導応用について、具体的な応用分野と装置原理および開発経緯の概略を説明できる。
E433 電気通信法令
Telecommunications Law
電気通信事業法は昭和60年に施行され、電気通信事業の分野に競争原理が導入された。その後も電気通信の技術革新、インターネットならびに携帯電話の普及などの環境変化に対応しその都度同法は改正され今日に至っている。電気通信事業の実施ならびに電気通信主任技術者の国家試験受験のために必要な電気通信法令の知識を修得する。
行動目標●主となる電気通信関連の法令の体系および目的を理解し、説明できる。各法令の内容および用語を理解し、説明できる。各法令について事例に対応させて理解し、説明できる。電気通信技術者資格試験の問題を解くことができる。
E905 専門ゼミ
Preparatory Seminar for Design Project III
移動通信システムまたは情報ディスプレイに関するプロジェクトデザイン III の新しい課題を自らが提案し、これまでに修得した知識・技術を用いて、その課題を解決するための方法を概略的に定めることができる。これにより、技術者として総合的な能力を活用するための基盤を築くことができる。
行動目標●プロジェクトデザイン III のプロジェクトの目標や行動計画について明確なイメージを持つことができる。プロジェクトデザイン III のプロジェクトのテーマ概要について説明ができる。プロジェクトデザイン III を自主的に実施するための基礎的な知識や技能を修得できる。設計や研究のプロセスが修得できる。
E925 プロジェクトデザイン III
Design Project III
これまでに学んできた情報通信工学分野の基礎を活かし、技術的発展に必要な「解決すべき問題点や課題」を見出す能力、およびそれらを解決し開発する能力を身につけることができる。そのために、プロジェクトテーマの実験と理論検討を通じて、基礎科目を復習し、高度専門知識を修得しながら、「移動通信技術」、「情報ディスプレイ工学」、「電子回路技術」、および「それらの応用技術」を身につけ、工学的センスを自らが高める。
行動目標●テーマの目的を明確にして、計画を立てることができる。テーマの解決法を自ら具体化して、管理しながら安全かつ継続的に実行することができる。社会のニーズと照らし合わせて、実験結果を正確に解析し、評価することができる。テーマの位置づけ、実験結果の意義を的確に説明することができる。プロジェクトテーマを論理的にまとめることができる。
E945 進路セミナー I
Career Planning Seminar I
自分の将来の進路、技術者としての職業観の形成を計り、自分に適した進学・就職の目標を設定すること、およびそのために必要な準備・対策に自主的かつ意欲的に取り組むことを目的とする。主な課題は3つある。①自己分析とキャリアデザイン、②進路アドバイザーや企業人技術者の講演、工場見学などを通して職業に対する意識向上を計り、自分に適した進路の在り方を探究する。③資格取得、一般常識、総合適性検査(SPI)など準備・対策に比較的長期を要する課題に計画を立てて着手する。
行動目標●人生設計と進路との関係を自ら深く考察できる。自分に適する進路を発掘すべく、それに必要な思考や行動ができる。進学・就職など自分の進路に関する方針や目標を自ら立案する方法を修得し、立案できる。進路に対する目標を達成するために必要な知識、能力、資格などを調査し、自ら準備・対応ができる。
E955 進路セミナー II
Career Planning Seminar II
自分の将来の進路、技術者としての職業観の形成を計り、自分に適した進学・就職の目標を設定すること、およびそのために必要な準備・対策に自主的かつ意欲的に取り組むことを目的とする。主な課題は3つある。①自己分析とキャリアデザイン、②進路アドバイザーや企業人の講演、先輩達の体験談聴講などを通して職業に対する意識向上を計り、自分に適した進路の在り方を探究する。③資格取得、一般常識、総合適性検査(SPI)など準備・対策に比較的長期を要する課題に計画を立てて着手する。
行動目標●自分が目指す進路を選択できる。進路選択に必要な情報の収集ができる。各種模擬試験の結果から自己の適性を冷静に判断できる。自分の思っていること、考えていることを相手に明確に伝えることができる。