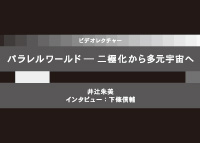下條 本日はお忙しい中、お時間を取っていただきありがとうございます。本当なら、当日会場に来ていただきたかったんですが、学校のご都合ということでビデオ取材という形を取らせていただきます。まず井辻さんは実作者であり、歌人でもあられるということで、そこでおそらく、本当は事実ではないんだけれどこうだったらどうだろうという、いわゆる反実仮想がいろいろと問題になってくるだろうというのが1点。そして他方では翻訳家、評論家としてもファンタジーの世界を広く見渡してこられて、おそらくそこで、さまざまなパラレルワールドに関する見聞をお持ちだろうというのが1点。その両面からお話をうかがえればと、お尋ねした次第です。本日はよろしくお願いします。
井辻 こちらこそよろしくお願いします。
『指輪物語』から始まるファンタジーの変革の歴史。
下條 さっそくですが、ここに先生の著作を数点ご用意しましたが、これらの著作の中で、『指輪物語』や『ハリー・ポッター』といったファンタジーのベストセラーのことが語られているんですが、1980年代から90年代にかけて、ファンタジーの枠組みが変わってきたのではないかというようなことを書いていらっしゃいますね。まず、そのあたりのことからお話ください。
井辻 先ほど反実仮想というふうにおっしゃったんですけれども、ホントに80年代くらいまでは、まともな日常世界があって、別に想像の世界があって、そこに行くのにはものすごく敷居が高かったんですね。作家の側もどういう仕掛けでこちらの世界から向こうの世界へ行くかをものすごく苦労していたし、読む側もここからは別世界の話なんだと峻別していた。それだけ現実がはっきりあった時代だと思うんです。それが21世紀になると、すっかりバリアフリーになってしまって、現実と非現実の境がなくなってしまった。ファンタジーを考えたり作ったりする側としては、つっかえ棒を外されたと言いますか、抵抗を失ってのめってしまうような感覚があるんです。かつては別世界に対する抵抗感が生み出していた切なさや憧れといったものが消えてしまって、今はすぐ隣にある世界、まさにパラレルワールドという感じになってきてしまっているんですね。
下條 作る側としてはやりにくくなっているということですか?
井辻 そうですね。そういうところはあると思います。そして歴史的には多分、トールキンが1950年代に『指輪物語』を書いてますけれども、そこで彼がファンタジーを大きく転換させたんですね。それは何かというと、主人公による冒険譚を書くのではなくて、世界を創ってしまう、準創造、サブクリエイションという言葉を使っていますけれども、創るという言葉を使ったわけです。それまではあるかないかが問題にされていて、どこにもないような夢物語の世界を書くなんてという非難をされていたんですが、ないならあたかもあるかのように創ってしまえというのがトールキンのスタンスだったんですね。ですから、騎士やホビットが出てくる古い世界を、その世界全体をリアリティを持って作った。ファンタジーではなく普通の小説と変わらないスタンスで書いたわけです。その意味では、オーラとか不思議で希薄な空気感とかはなくなりますが、逆にものすごく日常的なリアリティに満ちている。前景に押し出して、ホビットの性格から、村の様子、産物、神話、ライフスタイル、とにかくすべてを創ってしまえばいいと考えて、実際に創りあげてしまった。それでトールキンは本当に無駄に多い膨大なデータベースを準備して、その上にいくつかの話をのせていった。ある意味、スターウォーズと同じことをすでにあの時代にやっていたわけです。
下條 その無駄に多いという部分は説明がいると思うんですが、物語の本筋とは関係のないディテールまでもとにかくすべて創りあげてしまうということですね。
井辻 そう、トールキンという人はとにかく世界を創りたい人だから、世界にあるものはすべて書かないと気が済まない。ですから必ずしも物語に使うとは限らないいろいろなディテールを考えることをすごく愉しんでた人なんですね。部族の紋章をデザインしたり、中に出てくる古い書物、ザルグルの書というんですが、わざわざその現物を創ったりしてる。それも焼け焦げまでつけて。想像の世界にあるものをすべて物質化したいというか、こちらの世界に持ってきてリアリティを持たせてしまおうという発想です。
その後にミヒャエル・エンデが出てきまして、これは唯一日本だけでの大ブームだったんですが、『ネバー・エンディング・ストーリー』を書いたわけです。彼はシュタイナー思想を学んだりして、ちょっと変わった人なんですね。彼の面白い言葉があって、「私はビジュアルにできないモノは書かない」というのがあるんです。多分、それまでそんなことを言った作家はいないと思うんですね。これは今のビジュアル・ファンタジーの先駆け的な発想で、目に見えてくるモノをただ書いているというわけです。ですから、因果関係が説明できないような部分があったり、シュールレアリスムの絵のようなところがあるんです。
下條 視覚的な臨場感みたいなものなわけですかね?
井辻 そうですね。説明はしない、解釈はしたくない。ただそういうふうな絵が浮かんでくるから書くんだというスタンスですね。ですから、ある意味、物語がちょっと解体されてるのかもしれません。
そして、その後に出てくるのが『ハリー・ポッター』。あれは過去の昔話からいろんなフォーミュラ小説の集大成でほんとうにすごいんですけど、一番面白いのは、別世界とか異世界とかがまったく特別なものじゃなくなっている点ですね。それまでは麻薬を使ったり、詩人のような夢想家だったりしないと、向こうの世界に行けなかったものを、ホントに身近なものにしてしまった。すでにトールキンの頃からかなり散文化され始めていましたが、それを現実にくっつけて創ってしまったのがこの物語だと思います。学生たちもよく、『ハリー・ポッター』では別世界が自然に隣に存在している点がすごいと言ってます。
下條 今のお話には2つほど要素があるように思います。1つは過去のいろんなものを寄せ集めてくるということ。たしかに『ハリー・ポッター』を見ていると、どこかで聞いたような、見覚えのあるエピソードが多い。そしてもう1つは時空間を超えて、お構いなしに集める。これは博物館の発想ですよね。本来は隣にあるはずもないものをお手軽に集めてきてしまう。
井辻 もう祝祭空間ですよね(笑)。とくにパラレルワールドを扱った小説は、文学では間テクスト性というのですが、いろんなものから引用して創ってしまう。古い話で言えば『ドン・キホーテ』もそうだったわけですが、とくに『ハリー・ポッター』の場合は自然にそれをやってしまって、過去の文学遺産の面白い部分をピックして再編集して創っている。それこそホラーから学校小説から何でもありなんです。ですからそれ以降の魔法使いものは、そういうパッチワーク手法になっています。それは、映画というメディアで、CGがみんなの目に馴染んできたということも大きいかもしれません。『ハリー・ポッター』の映画はホントによくできていましたから、ああいう世界があるということに疑問すら抱けなくなるんじゃないかと思うんですね。少なくとも脳内映像では納得してしまう。
リアル化するファンタジー、その未来は?
下條 今のお話は『指輪物語』からエンデ、そして『ハリー・ポッター』というファンタジーの流れをわかりやすく説明していただいたわけですが、素朴な疑問として、なぜファンタジーの枠組みみたいなものが、1作品にとどまらず時代精神として、また文字に書かれた物語にとどまらず広い分野で、広く変化してきたんでしょうね?
井辻 ずっとファンタジーをやってきたものにとっては、われわれの願望がついに実を結んだという印象があるんですが、そういう潮流は幻想文学にはあったんですね。
下條 でもそれが世の中でメジャー化したわけですよね。
井辻 そうですね。それはまず、トールキン以来何でも創ればいいということになって、そんなもの嘘だろうという議論がなくなってしまったこと。そしてテクノロジーが進化して、ディズニーランドのような装置ができたし、映画監督はCGを駆使してもそういう物語を撮りたいんですよ。あり得ないものを現出させたいというクリエイターの人たちの熱意が入ってきたわけです。
下條 そのテクノロジーというのは?
井辻 それはつまり、詩人の頭の中にしかないと思われていた非現実なものを、物質化できる装置ですよね。たくさんの人々の五感に訴えかけられる装置、それはCGの技術といったものですね。
下條 そういう環境下で育った世代がだんだんファンタジーのメインの読者なり観客なりになってゆくと。
井辻 それに加えてゲームの影響も大きいですよね。トールキンのデータベースからゲームが出てきたんですが、ゲームで育った世代は、ちょっと違う世界に行って違うキャラクターになるというのは、日常的にすぐできてしまう。それはつまり異世界との往還がとても自然なものとして刷り込まれているわけです。その意味でゲームの影響力は大きいと思います。彼らは何の抵抗もなくファンタジー的な世界の物語を読んだり、映画を観たりできてしまう。
下條 今のお話を聞いていると、そうなんだと言いつつ、何となくそれが残念であるというようなニュアンスを感じますが? つまり思い入れや畏れが失われているのかなと。そういったことも含めて、ファンタジーは今後どうなっていくとお考えですか?
井辻 そうですねぇ。今はもう、ファンタジーとそうでない小説の違いがほとんどなくなっていて、昔はマジックリアリズムなんて言い方もありましたけど、今はほとんどすべてのファンタジーがリアリズムの手法で書かれています。ですから、別世界というものに対する違和感や憧れといったものがなくなって、自然と自分のホームグラウンドに入ってきているという状況だと思うんですね。そんな中で、じゃあ次にどこへ向かうかというと、次に来るファンタジー文学の感動は、この現実を含んだ上で、より大きな現実に再構成、再編集して見せてくれるような作家によってもたらされるように思います。というのは、現在、私たちはかなり断片的な世界に生きているような感じがするので。
下條 何か念頭に置かれている作品なり作家なりはありますか?
井辻 例えば、ラルフ・イーザウの書いた『ネシャン・サーガ』 は、20世紀史をパラレルワールドの形で、表の歴史と裏の秘密結社の陰謀とを絡めて語り直すものです。20世紀をまったく違う形で見せてくれています。
下條 スケールは小さいかもしれないけれど、『ダヴィンチ・コード』もそういった部類に入りますね。
井辻 そうですね。つまりわれわれの知っている歴史にもう一筋つけることで倍になって、より大きな価値観で見えてくる。あとフィリップ・プルマンのライラの冒険シリーズという三部作があって、これは聖書の語っているあるべき人類の流れに異を唱えて、神は実はオーソリティという名の年取った天使に過ぎなかったとか、キリスト教的な世界観とは違う、もう一つの壮大な世界観を描いています。
下條 なるほど。とても興味深いお話をありがとうございました。 |