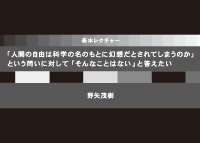下條 では次のゲストをご紹介します。東京大学の野矢茂樹先生。哲学のベストセラーでみなさんよくご存じかと思います。実は彼は私と高校の同級生でして、生意気でええかっこしいだけど頭のいいヤツがいるなぁと思ってたんですね(笑)。学校の行き帰りによく難しい話をしていたように記憶しています。その後、大学でも学科こそ違え、よくキャンパスで会うようになり、私も哲学ファンでしたから、野矢先生のご師匠である大森先生のゼミに一緒に出たりしていました。ま、そんなことで、私にとって彼はオールマイティのジョーカーでして、どんなテーマでもお願いできる存在だったわけです。
で、今回、ついにお願いすることができました。私はパラレルワールドと自由は何か関係があるのではないかと思っていまして、野矢先生はまだ、自由についてそれほど語っていらっしゃらない。そこで野矢先生には、哲学の立場から「自由」について語っていただこうと考えたわけです。では、よろしくお願いします。
野矢 野矢です。よろしくお願いします。今、ご紹介いただきましたように、これから「自由」についてお話しするわけですが、私がここで考えようと思っているのは、大変ささやかな自由でして、例えば、今、私は手を挙げました。この手を挙げたのは、私が自由に手を挙げたと言いたいのです。つまり、手を挙げる自由を確保する、ただそれだけのことです。それ以上、いろんな意味の自由があるけれど、それらの一番基本にあるのがこの、手を挙げる自由だと思います。ではこの手を挙げる自由というのは何を意味するかというと、それはつまり、「手を挙げた、でも、挙げないでもいられた」ということです。このことを確保したいと思います。
しかしこの問題は、論争できないんですよ。今、私が手を挙げたときに「挙げないでもいられた」と言っても、隣にいる下條さんのような人から「いや、そんなことはない」と言われたら、反論のしようがないんですね、実際、挙げちゃったわけだから。でも「君は手を挙げるように決められていたんだ」と言われると、逆に私の中には「そんなことはない!」という、ものすごく強い実感があるわけです。でも、一旦挙げてしまった以上、挙げないでもいられたことを証明することはできないわけです。
佐藤先生の多世界解釈のお話の中の、世界がどんどん分岐していくというお話は、もしかすると自由にとって足しになるのかなと考えながら、うかがっていました。が、残念ながら、足しにはならないなぁ、という結論なんですけどね(笑)。それはつまり、多世界解釈によれば、過去において無数に分岐した一つが私たちの今の世界なわけです。そしてこれからもまた、分岐してゆくという。だけれども、私が手を挙げたときに、別の世界に手を挙げなかった私によく似た人がいたとしても、この私の自由には何ら関係がないんですよ。私が言っているのは、手を挙げちゃったこの私を何とかしてくれという話ですから。挙げちゃった私が「それは決められていたんだ」と言われたときに、それに対してどう言い返したらいいかを今日は皆さんに伝授したい。いや、そんなに偉そうな話じゃなくて(笑)、反論するための私なりのアイディアを聞いていただこうと思います。
自然科学は、決定論的な法則など与えない。
「君は手を挙げるように決められていたんだ」と言ってくる人は、自然科学、基本的には量子論以前の古典力学ですが、をバックグラウンドに持っています。これを決定論というわけですが、まず、決定論というものを簡単にご説明しておきます。
決定論というのは、この世界が決定論的な法則に従っているという考え方です。因果法則に限るとちょっと狭くなってしまいますが、ここでは因果法則で説明させていただきます。ある出来事Aが起きると、それによって必ず、出来事Bが起こる。常にAの後にはBが起こる。このように、例外を認めない厳密な因果法則について考えたいと思います。
世の中には大まかな因果法則というのも多々あります。例えば、腐ったものを食べればお腹をこわす。これは一概には言い切れません。とても体調が良ければ、乗り越えられてしまうかもしれない。厳密な因果法則は、こんないい加減なものじゃあありません。そして決定論というのは、この世の中に起こる物事はすべて、何らかの厳密な因果法則に従っている。つまり、私が手を挙げたことも、厳密な因果法則の結果であり、挙げないでいることはできなかったのだ、という立場です。私にとって、過去は1つです。今ここに立ってしゃべっている私が生まれてから通ってきた過去は1つしかありません。その過去が1つに定まっているということは、原因が定まっているということです。そこに厳密な因果法則をかけたら、未来も全部決まってしまうわけです。そうすると、過去から未来まですべてが決定されている、という話になってしまう。
さて一方で、哲学の世界には両立論というのがあります。決定論と自由は両立するんだという論陣が、そんなに少数派ではなく存在しています。でも私は、その立場は弱腰というか(笑)、何を言っているんだと思うわけです。もしも、私が手を挙げることが何かに決定されていたとしたら、それはまったく自由の可能性を奪い去ってしまうものだと、私は考えています。ですから私はここで、決定論は間違っていると言わなければならない。でも、正直、怖いんですよね。私は佐藤先生はいずれノーベル賞を取るんじゃないかなと思っているんですけど、そんな大先生の前で、これから決定論を否定するわけですから(笑)。
でも、もじもじしてたら時間がなくなってしまいますので、とっとと言いましょう。「自然科学は、厳密な因果法則なんてまだ1つも提出していない」。ふぅ、言っちゃった(笑)。もちろんすべてを調べたわけではないので、ホントに無責任な発言なんですけど、2、3の事例を紹介しながら、説明させていただきます。
まず、中学で実験したと思いますがフックの法則。これはバネのような弾性体の伸びと荷重は正比例するという法則なわけですけど、ところがこの世の中に、フックの法則に当てはまるものなんて1つもないんです。それはなぜかというとフックの法則の前提は、その弾性体が完全に均質であることです。だけどまったくムラのない弾性体なんてありはしないんですね。どこかにムラがある。
もう一つ、例を出しましょう。ボイル=シャルルの法則。「気体の圧力は体積に反比例し温度に比例する」というヤツですが、これもまた世の中にこの法則を満たす気体なんてありません。これが成り立つのは理想気体と呼ばれるもので、分子の間で相互作用する力を0と考えた気体なわけです。そんな気体はあり得ません。よってこの法則も成り立ちません。
次に、万有引力の法則。これは、もしも宇宙に2つの物体しかなければその物体間にこれこれの力が働くとする法則です。しかし、2つの物体しかないなんてことはありませんから、万有引力の法則もまた、厳密に成立している事例というのはない。
ただし、私は何も、自然科学にケチをつけようとしているわけじゃあありません。むしろ、このように基本法則と現実世界とのズレを見せることこそが、自然科学の持っている生産力の大きな源になっていると思います。ですから、自然科学はこのズレをもっと創りだし、もっと利用すべきだと思うわけです。
しかし、これらの基本法則はAが起きれば必ずBが起こるという厳密な因果法則ではないわけですから、これは世界のあり方を描写したものだと考えるのは誤りなわけです。これらの基本法則は世界のあり方を描写したものではなく、それは自然科学の探究の指針を表したものだと、私は言いたい。そのことを後半で説明します。
私の自由を確保するために、私は因果法則を出し抜き続ける。
基本法則は自然科学の探究の指針を表したものという考え方を説明するために、科学の歴史で一番印象的だった事例をパラダイムケースとしてご紹介します。ニュートン力学についてです。かつて、天王星の軌道を観測したところ、ニュートン力学での計算結果と違っていた。基本法則との間にズレがあったわけです。その時に自然科学は、ニュートン力学を疑うのではなく、何かズレを生じさせるような原因があるはずだ、と考えました。つまり、天王星に影響を与えている未知の力があるはずだ、と考えたわけです。そして、海王星を発見しました。1846年のことです。これは素晴らしくドラマチックな結果でした。
これを私なりに解釈するとこうなります。基本法則というものは、現実世界との間にズレを持っている。そのズレを説明するような要因をこの世界に探してゆく。この時に基本法則が果たした大きな役割というのは、自然科学にとっての探求の対象を探し出す、昆虫の触角のようなものなわけです。つまり、現実世界に基本法則というバイアスをかけると、基本法則とズレている部分が浮かび上がってきます。そのズレを見つけ、そして基本法則を守るような原因を見つけ、説明をしてゆく。この解釈が自然科学の活動を的確に捉えているのであれば、次のようなことになります。自然科学は世界のあり方が決定論的であることを示したわけではなく、厳密な因果法則で世界が成り立っていると考えて世界を見るといろいろなことがわかるから、このやり方で世界を探求している。これが意味するところ、基本法則は世界を描写したものではなく、探究の指針だということです。
では、それが私の自由とどう関係してくるのか。ここから先は独断ですが、厳密な因果法則と世界のあり方との間のズレは永遠に解消されないだろうと思うわけです。そしてまた、解消する必要もないでしょう。もしも、厳密な因果法則を見つけたと主張する科学者が現れたとしたら、私自らが身体を張って、ズレを創り出す準備があります。
というのは、人間の行為というのは、まさにわれわれが自由だと確信している行為は、厳密な因果法則から常にズレを創り出せると思うんです。つまり私が左手を挙げる行為に対して、厳密な因果法則が提示されたとしたら、私はその因果法則を裏切るような行為を採ることができる……はずだ……と思う(笑)。でもそういうことだと思うんです。ただ、向こうがそういう厳密な因果法則を出してきてくれていないから。
例えば「あなたは5分後に左手を挙げる」という予言を法則に基づいて出してきてくれたら、私は5分後に挙げなければいいわけで、もしその時に本当に左手が勝手に挙がってしまったら、私は哲学的な立場を換えるかもしれません(笑)。だけれども、私は厳密な因果関係を裏切ることができると、強く確信しているんです。この話は、私の先生でもあった大森荘蔵さんが自由と決定論を論じたときに「予言破りの自由」という言い方をしていたものです。これは論証でも何でもないんですが、確信ですからどうしようもない。
ただ、私が何か決定論的な因果法則を裏切る行為をしたとすれば、自然科学の側はまた、そのズレを説明するようなファクターを出してくるでしょう。そうやって自然科学は改良してくる。それがまさに海王星の発見につながってゆくわけです。ただ、私はまたその説明を裏切るわけです。するとまた自然科学は改良する。イタチごっこです。それも永遠に続きうるイタチごっこなわけです。その確信こそ、私が自由であることの実質だと私は考えています。以上が、私のアイディアです。 |