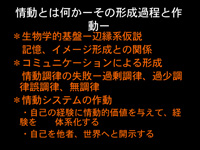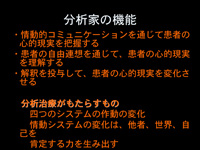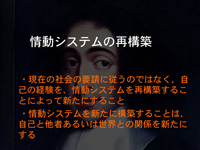今日のテーマは無意識と情動です。僕が情動に関心を持ったのは10年ほど前からです。僕は構造主義の影響を受けていましたから、当初は言語への関心のほうが強かった。ところが自分の関心がスライドしていき、現在は情動的なるものが一番の関心の対象になっています。
かつて僕はラカンに傾倒していたのですが、ある時、ラカンの理論がまったく無意味に思えてきた。それは僕が臨床をやっているからです。これには時代の流れの影響もあると思いますが、構造主義以降の時代、人々は言語をあまりにも中心に考えすぎのではないでしょうか。それに対する修正、もしくは新たな理論の構築が必要だと、僕は思っています。アンドレ・グリーンはラカンの理論を情動の観点から理論化しています。ただそれは構造という枠組に収まってしまっていて、情動はそのような枠組としては捉えることができません。といって、フロイトのようなエネルギー論でも取り扱えません。もう少し別のアプローチが必要だろうと僕は考えています。
さて、本論です。精神分析家的観点から見た情動についてお話をします。まず歴史的観点をおさらいして、その後に情動と現代社会の関わりについてお話ししたいと思います。
精神分析の歴史における情動
精神療法の歴史において、18世紀以降、情動関係は治療促進的だという発想がありました。メスメルの動物磁気治療、リエボーの暗示療法などが情動に関わる精神療法としてあげられます。そしてその後、情動の歴史を考え語る上で重要な、シャルコーの催眠療法に至ります。
シャルコーの催眠療法は動物磁気の流れを汲んだもので、情動を媒介として患者のヒステリー症状を誘発することによって、その症状を取り除くというものです。シャルコーの功績は、それまでいかがわしいと思われていた精神治療をアカデミズムの俎上にあげた点にあります。サルペトリエール病院の神経科部長という権威ある地位にいたシャルコーが催眠療法をとりあげたことで、催眠療法が格段の信頼性を得たわけです。この絵に見られるようなシャルコーの臨床講義というのは、舞台装置のようなもので、数多くの知識人を魅了しました。(*1)意図的に女性患者のヒステリー症状を引き起こすという治療は、ドラマ的なスペクタクルとしては非常に興味深いものだったわけです。催眠療法においては身体的接触が重要な手段であり、またシャルコーと女性患者とは支配するものと支配されるものという関係にあったわけです。
この現場に参加して感銘を受けたのがフロイトです。しかしその後フロイトは、催眠は暴力であるとして催眠を放棄するようになります。1890年代のことです。そしてフロイトは1921年の「集団心理学と自我分析」の中で次のように説明をしています。
フロイトにとって、集団というのは催眠関係によって形成される構造です。集団とは相手に対する一目惚れ的な過度の理想化であり、従属や無批判が生じ、自分の最も重要な自我理想を相手に重ね合わせてしまう。これが集団形成の一般的法則だとフロイトは書いています。次のスライド(*2)は、右が1885年の催眠療法の絵、左が1921年のウィーンのファシズム的な風景ですが、フロイトは催眠状態に基づいた集団の形成というのはファシズムの一形態であって、指導者を自我理想として結束した集団だと論じています。そしてこの二つを情動関係で見れば、まったく同じ現象だとフロイトは考えたのです。
催眠に示されるような情動関係においては、1つには治癒的な側面があります。もう1つは患者をコントロールして従属させる暴力的な側面があります。そしてフロイトは、自由連想という方法をとることによって、この暴力的な側面を取り除こうとしたわけです。
では、フロイトは情動をどのように考えていたのでしょうか。フロイトが情動という言葉を使ったのは初期だけですが、フロイトは情動をエネルギーの量だと捉えていました。ヒステリー患者においては外傷的な出来事の記憶、つまり表象に強い情動が付加されることで、症状が形成されている。そして重要なことは、フロイトが情動と表象を一体化可能な対の概念として考えていた点です。しかし言語やイメージといった表象と情動は、果たしてそのような関係にあるのでしょうか。ロバート・ザイアンスの単純接触効果の実験などから、情動と認知は独立したシステムとして、つまり情動の作動は対象の認知、表象とは切り離されていると考えられます。このような考え方に基づくなら、フロイトの発想は、前提からして間違っていたことになります。表象の水準での操作をいくら行っても、情動の作動を変えることはできません。これがフロイトの治療上の失敗の原因の一つであったと考えられます。
フロイトの情動への関係は、催眠を断念することで一時期薄れたわけですが、その数年後、フロイトは転移を発見し、1905年のドラの症例において、転移は使い方によっては最大の武器になるとも言っています。ここにおいて、情動は転移という姿で再びフロイトの前に現れたことになります。そこでフロイトは転移を解釈することが精神分析の最も中心的な課題であると考えるようになっていきます。それまでは個体内の問題であったものが、個体間、つまり分析家と患者の間の問題にスライドしたわけです。付け加えれば、フロイトはこの段階では分析家は患者からアフェクトされてはいけないと考えていました。
精神分析に見られる情動
ここからは、情動の一般的な問題についてお話したいと思います。(*3)
言語と違って、情動は生物学的な基盤を持っています。情動は複数のシステムから成り立っていて、記憶やイメージの形成と結びついています。さらに情動の形成には、コミュニケーションが関与しています。なかでも重要なのは、母子のコミュニケーションです。ダニエル・スターンが母子の情動調律について詳しく説明していますが、まだ言葉をしゃべれない子どもと接しているとき、子どもの言語にならない意思表示を母親がうまく調律していくと、子どもは他者や世界を肯定的に把握することができるように成長していきます。このように形成された情動システムが自己の基盤を形成し、情動システムによって自己は過去と未来を繋ぐことができます。何かの経験をすると、経験には情動的な価値が付加され、記憶の中で体系化されていくわけです。
ところで、人間にとって最も重要なことは他者とどう生きるかという問題に尽きるのではないでしょうか。そして、情動こそが自己を他者に開いているのです。情動と言語によって自己は他者に開示しています。例えば自閉症の患者を見ていると、彼らは言語を習得してはいますが、他者には開かれていない。それは情動による他者への開示が為されていないために、言葉がコミュニケーションとしてではなく、単に記号としてしか使われていないためです。
次に、現代の精神分析において情動がどのように考えられているかという点について、ラカンとビオンという2人の分析家で見てみましょう。まずラカンについて言えば、ラカンの理論においては、情動と感情が混乱した形で論じられています。そして基本的にラカンが扱っているのは感情の問題で、情動に関しては彼は不安しか取り扱っていません。不安は人間を騙さない、ゆえに不安こそが分析治療の指針になると、ラカンは考えています。ラカンにとって人間とは、不安という情動と言語とによって規定された生き物ということになります。一方ビオンは、乳児と母親、患者と分析家の関係をパラレルに考えています。このモデルは非常に素朴で、この2つの間には当然ギャップがあります。子どもの経験と大人の経験を同じ水準で考えていいわけではないのですが、この構想自体は非常に優れたモノだと言えます。つまり不快を自分の中で処理していくような過程、現実の痛みをそのまま受け入れる力こそ思考の力だと、ビオンは考えるわけです。
現在の私たちが置かれている環境
さて、僕は今システムという観点から分析理論を再構築できないかということを考えています。(*4)精神分析というのは言わば、患者の情動システムを新たに形成し直す治療です。この情動システムに現在最も大きな影響力を持っているのは、精神分析ではもちろんなく、薬物です。とりわけSSRIをはじめとする抗鬱剤ということになります。この薬物は現在、鬱病に限らず、パニック障害や過食症などにも適用されています。このことが問題なのは、それが資本の論理によって左右されている点です。
このSSRIという抗鬱剤に代表されるように、現在資本はわれわれの情動システムの内部にまで介入し、不安や不快のない個人をつくり出そうとしています。それはもちろん私たちのためではなく、資本の論理が要求していることです。私たちの情動システムはこのような論理に基づいて構築すべきものではないと思います。もしそのような論理に従ってしまうと、情動の持つ可能性が、一切失われてしまうことになります。例えばベルグソンが書いているように、情動は創造性と結びついていますが、それも失われてしまいます。(*5)
精神分析というのは、こういった資本の論理に対抗可能な一つの思考法であると言えます。情動システムを新たにするということは、私たちの自己と他者もしくは世界との関係を新たにし、そして世界を新たにつくり出すということです。世界を新しくつくり出すということは、自己を新しくつくり出すということです。それゆえに、私たちはこの情動の持っている可能性をやすやすと捨てるべきではないのです。
|